日本では高齢化が急速に進行し、マンションの居住者も高齢者が増加しています。国土交通省による令和5年度のマンション総合調査によると、60歳以上の居住者が半数を超えるマンションも少なくありません。
このような状況で、安心安全な生活環境を維持するためには、具体的な対策が不可欠です。本記事では、マンション管理士が日々直面する高齢化問題に対応するための20の安心安全対策を紹介します。
防犯、災害対策、バリアフリー化など、すぐに実践できる方法から大規模な改修まで、幅広く解説します。
※対策の優先度は、マンションの管理状態や財政状況により異なります。
高齢者が多いマンションの安心安全策をマンション管理士が20例紹介
今回紹介する内容は以下の通りです。
筆者の推奨として、是非取り入れたい★★★★★~管理組合としてコストが許せば検討したい★ということで、分けて紹介します。
・高齢者向け防犯対策:マンションでできる4つのポイント ★★★★~★★★★★
・災害時の避難計画:高齢者に配慮した3つの対策 ★★★★~★★★★★
・居住者名簿の重要性と管理 ★★★★
・高齢者向けコミュニティ形成:4つの交流促進策 ★★★~★★★★
・見守りサービスの導入と活用方法 ★★★
・バリアフリー化の必要性と5つの改修ポイント ★★~★★★
・エレベーターの改修・新規設置 ★~★★
高齢者に対する安心・安全対策を全部で20例抽出しました。
紹介の順番としては、費用が極力掛からないもの→高額な修繕費用等が発生するものの順番で紹介します。
とりわけ、★が多い対策については、費用を掛けない範囲でもまずは管理組合で対応可能かを検討したいところです。
このあとの高経年マンションを中心とした現状でも紹介しますが、経年が進むとマンション内の劣化も増加し、修繕箇所が多くなります。
また、それと並行して高齢の区分所有者によっては修繕積立金の負担が重くなってくることも考えられます。
したがって、対応する人や金銭的なリソースがあるマンション管理組合としては、「できる所から実施する」が基本線になってくるでしょう。
高齢化社会のマンション管理:直面する課題と解決策
マンションの「二つの老い」とは?
マンション管理組合が直面している「2つの老い」とは、
・住民の「高齢化」
という2つの問題です。
具体的には、
・高齢者が多いと、役員の順番が若い世代に早く回ってくる
などの影響です。
また、世帯主の年齢構成は、令和5年度マンション総合調査
によると、
・前回調査と比較すると、30歳以下は7.1%から6.2%へと減少する一方で、70歳以上は22.2%から25.9%へと増加
とのことです。
「2つの老い」については、以下の記事
に詳しく紹介していますので、今回はこちらをご案内します。
管理費・修繕積立金の滞納問題とその影響
必ずしも高齢者に限ったことではないですが、年金暮らしの高齢者の中には普段の生活で負担が多くなってくる方も一部には考えられます。
管理組合内で滞納があると、若い世代を含めた区分所有者全員に影響を与えてしまうこととなります。
また、修繕積立金不足となると、後述するマンションのバリアフリー対策をはじめとする、設備面における安心安全対策も後手に回ってしまう可能性も出てきます。
ちなみに、令和5年度マンション総合調査では、完成年次が古いマンションの方が滞納割合が高いというデータが出ています。
高齢者向け防犯対策:マンションでできる4つのポイント ★★★★~★★★★★

具体的に、高齢者に対する安心安全対策を確認していきます。
防犯対策や安全性の確保は、高齢者のみならず居住者全体に重要な論点です。
高齢者にフォーカスを当てると、具体的にはどのような対策が可能なのか、確認してみます。
地域の不審者情報を共有する方法
掲示板の掲示や、各戸へのチラシ配布、館内アナウンス等で周知することが求められます。
防犯意識を高めるための情報共有と説明会
ついつい自分の家族からの要請ということで、大切なお金を振り込もうとしてしまいます。
振り込み詐欺かどうかのチェック方法や相談先など、高齢者に対する対策としては管理組合としても重要でしょう。
さらには、高齢者に限らず、マンション管理組合全体として普段から心がけておきたい防犯対策の共有も考えられます。
そして、これらの啓もうのための説明会を実施することも対策の一つとして考えられます。
玄関ドアと窓のセキュリティ強化
比較的新しいマンションでは、防犯に配慮した玄関ドアや窓ガラス・窓サッシにおいてはセキュリティ対策が施されています。
しかしながら、経年マンションでこれらを取り換えたことが無い場合は、十分でないことも考えられます。
共用部分の防犯対策:管理組合の役割
こちらは費用がある程度かかってしまうこととなりますが、安心、安全には変えられないという視点から、管理組合として検討することも考えられます。
災害時の避難計画:高齢者に配慮した3つの対策 ★★★★~★★★★★

続いて、こちらも高齢者に限らず、居住者全員にとって大切な論点ですが、若い方が中心のマンションよりも配慮しなければならない事項も存在します。
具体的にどのような対策が必要なのか、確認していきます。
安全な避難ルートの確保と定期確認
また、廊下や共用部分に居住者の私物が置かれていないかどうか、定期的にチェックしておくことも重要です。
避難経路として、建築基準法上の廊下として片側のみ住居がある場合は幅1.2m、両側に住居がある場合は1.6mの通路幅が確保できているのかも重要な点です。
なにか工作物によって、幅が確保できていないことも比較的考えられます。
また、義務化されている消防法による法定点検により、問題なく機器や設備が整っている状態であるかも重要でしょう。
非常用備蓄の充実:高齢者世帯に必要なアイテム
比較的若い世帯と比べて高齢者世帯においては、万が一災害が発生した際においても、柔軟に動くことができないことも想定されます。
高齢者も参加できる避難訓練の実施
とりわけ、車いすで避難する場合はどのように考えればよいのか、また、身体的に不自由な居住者が安全に避難するような体制はどのようなものなのかなど、対応策を準備しておく必要があるでしょう。
居住者名簿の重要性と管理 ★★★★
ただ、個人情報になるため、管理組合としては取得の目的等を提示したうえで居住者からの了解を得て取得することが望まれます。
具体的な収集方法や注意点等、以下の記事
で細かく紹介していますので、そちらをご参照ください。
高齢者向けコミュニティ形成:4つの交流促進策 ★★★~★★★★
マンション内で高齢者が孤立しないように、気に掛けてあげるコミュニティづくりも管理組合として重要な論点です。
具体的にはどのような活動が有効的なのか、紹介します。
理事会・自治会での高齢者見守り
管理組合内では、高齢者が誰であるかある程度把握はしているでしょう。
しかしながら、最近見かけなくなったりすると、どうしたのかということで心配にもなります。
高齢者世帯への声掛けと手渡し配布
前述のような、最近見かけないという話題が出た場合は、管理組合役員や管理員さん中心に確認をすることも考えられます。
もし、管理組合内での配布物がある場合は、ポスト投函ではなく、呼び出しベルを押してあえて住居に訪問することも考えられます。
ポスト投函物の確認で異変を察知
玄関の集合ポストの郵便物がたまっている場合は、長期不在としている可能性もあります。
とりわけ、高齢世帯については気になる所でしょう。
自治会と連携したイベントの開催
また、マンションに独自の自治会が無い場合は地域の自治会・町内会と連携することによって、このようなイベントの参加を促すことも可能でしょう。
戸建てを中心とした、地域の自治会や町内会は高齢世帯も比較的多く、このようなイベントを定期的に開催している所も多いです。
マンション管理組合としても、地域の自治会・町内会組織とうまく連携することによって、独自開催するよりも負担を減らすことも可能です。
見守りサービスの導入と活用方法 ★★★
自治体や事業会社が見守りサービスを行っています。管理組合として具体的にどのような対策が可能なのか、以下紹介します。
地域の見守りネットワークとの連携
自治体においても、見守りについては課題として認識しています。
また、横浜市は認知症高齢者等に対する対策も実施しています。
見守りサービス会社の紹介
管理会社に委託している場合は、管理会社協力の下で連携して進めるのも良いでしょう。
バリアフリー化の必要性と5つの改修ポイント ★★~★★★

高経年マンションは、最近できたマンションと比べてもバリアフリー化に対応していない所もあり、解消が望まれる所です。
2006年12月に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)が施行され、マンションでもバリアフリーが一般的になっています。
しかしながら、それ以前のマンションは、一部対応であったり全く対応していない点もあるため、管理組合の必要に応じて対応が求められます。
ただ、バリアフリー化は一定の費用が掛かるため、管理組合としては是非補助金も活用したい所です。
また、具体的に共用部分において考えられるバリアフリー化は、以下のとおりです。
参考:国土交通省 国土技術政策総合研究所 安全・安心なマンションのために
通路の段差解消で安全な移動を
車いすで移動する居住者も比較的多くなっているマンションもありますが、段差があると、車いすのタイヤがうまく上がることができないこととなります。
共用部分における手すりの設置場所
高齢者が停止するエレベーターホールやロビー等、一旦立ち止まる箇所や、階段には手すりが必要となります。
マンション内を見渡せば様々な箇所に手すりが必要な場合も想定され、設置が求められます。
滑りにくい床材の導入で転倒防止
東京都消防庁のホームページ
によると、高齢者の事故のうち約8割が転ぶ事故とのことで、年々増加傾向です。
マンション内においては、廊下や階段がその原因として考えられます。
ある程度の予算化が必要なので、大規模修繕工事等に合わせて実施を考える必要があります。
廊下の照明改善で視認性向上
廊下やエントランス、外階段などにおいては、薄暗く歩きにくい箇所が発生する可能性があります。
また、段差に気付かずに転倒することも考えられます。
誰でも通行しやすいように、一定のスポットの照明を変更したり、光量が発揮できるものに変更することも考える必要があるでしょう。
また、照明が切れている個所がないかのチェックも欠かせないようにする必要があります。
出入口の扉を工夫してアクセシビリティUP
経年マンションにおいては、扉を手前に引いたり、押したりして開ける開き戸の所もあるでしょう。
イメージしていただければわかるかと思いますが、開き戸は車いすでは出入りが難しく、介助があっても手間がかかります。
そのため、開き戸から引き戸に変更することも考えられます。
ただし、スペースの関係上、変更できない場合もあるので、事前に十分確認することが求められるでしょう。
エレベーターの改修・新規設置 ★~★★
高経年の団地には、エレベーターが設置されていない所もあり、階上にあがるのも苦労します。
特に暑い夏は、最上階まで上がるのにも大変です。
エレベーターを新たに設置するということも考えられますが、修繕積立金からの支出が非常にかかってしまいます。
また、エレベーターがある住戸においても、かごの改修等で車いすでも入りやすくすることも考えられます。
既存エレベーターのバリアフリー改修
古いエレベーターであれば、最新型のエレベーターと違った設備になっていると考えられます。
具体的には、音声案内システムがなかったり、行き先ボタンの配置が高いところにあり車いすに乗ったままでは押せないなども考えられます。
また、エレベーターとエレベーターホールの間の隙間(しきい)の幅が広く、この間を縮小することによって、車いすや杖を持っている人でもスムーズに乗ることができます。
さらに、場合によっては手すりも必要になるでしょう。
そして、車いすで乗る方は周りを見渡すことが難しくなります。
そのため、周囲を確認することができるミラーの設置も考えられます。
エレベーターの新規設置
高齢者だけではなく、ファミリー層における普段の生活においてもエレベーターの有り無しでは利便性が全く変わります。
子どもがいる家族においては、重要なポイントであるといえます。
エレベーター工事には特別決議が必要
こちらは対策ではなく、注意点となります。エレベーターのかごやシステムの改修や新規設置は、これまで見てきたバリアフリー化と比べて大規模な工事(著しい変更)になります。
手すりやミラーを設置することは著しい変更には当たらないものの、著しい変更にあたる工事をおkなう場合は、区分所有者数及び議決権の4分の3以上の承認によって可決される、総会の特別決議が必要になる点に注意が必要です。
手掛けられるところから始める安全安心対策
高齢者が多いマンションでは、防犯対策や災害時の避難計画、バリアフリー化など、多岐にわたる対策が必要です。
管理組合としては、まず居住者のニーズを把握し、優先順位をつけて対策を進めることが重要です。また、地域の自治体や専門家と連携することで、より効果的な対策が期待できます。
本記事で紹介した20の対策を参考に、手掛けられるところから始めてみてください。







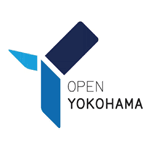






コメント