マンションの管理組合と町内の自治会
それぞれの役割が分かりづらいという方もいらっしゃるでしょう。
管理組合と自治会は似て非なるものです。
しかしながら、お互い連携しなければマンション管理は回りません。
それぞれの役割とともに、お互いにどうすればよい関係を築いていけるのか、確認していきます。
自治会に管理組合が団体加入していた判例
先日のマンション管理新聞に載っていた判例トピックです。
「住民で構成する自治会に管理組合が『団体加入』していた
ことが掲載されていました。
裁判の詳細
管理規約に、管理組合が自治会に団体として加入し、管理費から自治会費を払うという管理規約の有効性を東京地裁にて争った裁判です。
原告側は区分所有者、被告側は管理組合です。
地裁の判決として、
・自治会への「団体加入」は、「管理組合の目的の範囲内」だと結論付け、規約の有効性を認めた
とのことです。
管理組合における自治会加入の経緯は?
この事例で興味深い点があります。
自治会設立5年後に管理組合が自治会に関する細則を制定していることです。
その中で、自治会に支払う会費として、
管理組合が自治会に業務の一部を委任、
または
管理組合業務の補助を受けることの対価としての性質を有することを明文化
しているということです。
さらに、細則を制定したあとに、管理組合と自治会側で、
管理規約・細則を相互に遵守する旨の合意書
を締結していました。
判決は?
原告としては、この規約の条項や、自治会費の支払いを承認したことによる総会決議の無効性を提起していました。
・管理組合が自治会に対して業務を委任する
・そのために管理組合が自治会に加入する
そのような相互の関係を強化する取り組みでありました。
しかしながら、自治会の活動には、文化、スポーツ、レクリエーション活動やサークル活動もあります。
この活動が
加入必須である管理組合が、加入任意である自治会に加入することで間接的に参加
することとなっていることに、違和感を覚えたのかもしれません。
裁判長は、イベントやサークル活動も、
「その目的・内容によってはマンション・周辺環境の維持向上に資する活動として管理組合の目的に含まれる場合があり得る」
との見解も示していたそうです。
判決に対する見解
管理組合代理人弁護士からは、
「イベント等管理組合のコミュニティ活動や自治会との関係は2016年の国土交通省の国会答弁の見解で解消済みで、区分所有者の誤解に基づく提訴で残念だった」
とのコメントを残しているようです。
今回の判例は、管理組合が自治会に加入することの是非について問うたものです。
そして、分譲マンションの最大の問題である
「マンション住民の高齢化」
「マンション自体の高経年化」
という「二つの老い」とは関係のない所です。
自治会はマンション住民の高齢化が心配であり高齢者の安否を気にかけていることでしょう。
一方で、管理組合はマンションの高経年化による共用部分の劣化に対して対応をしていかなければならない立場にあります。
自治会と管理組合が協力しながら取り組まなければならない中、その関係において興味深い判例として取り上げました。
管理組合とは

判例の前置きが長くなりましたが…
管理組合とはどのような団体かを確認してみます。
管理組合とはどういう団体か?
区分所有法第3条には、管理組合の定義として
とあります。以下、法律の解釈となりますが、
「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し」
とあるのが「管理組合」のこととなります。
また、続きに
「集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」
とあります。
「集会」とは管理規約でいう「総会」
であり、
「管理者」とはほぼ同様の概念として「理事長」
として捉えることができます。
ここで、
最初のカギカッコは「団体を構成し」とあるのに対して、
後半の集会、規約、管理者の所は、置くことが「できる」
となっています。
管理組合への加入は義務?
あえて「団体を構成できる」となっていない点がポイントです。
すなわち、
団体は「構成されなければならない」
ということで、管理組合は任意でなく、
区分所有者全員の加入が義務となる団体です。
一方で、「できる」と記載がある、集会(総会)、規約(管理規約)、管理者(理事長)は極論すれば「なくてもいい」というのが区分所有法上の定めです。
よって、管理組合はマンションの所有者である区分所有者が法的、義務的に加入しなければなりません。
また、集会(総会)、規約(管理規約)、管理者(理事長)については、マンションの管理については無くてはならない存在であるため、区分所有法よりも実態に近いマンション標準管理規約に従った管理が望まれます。
自治会・町内会とは
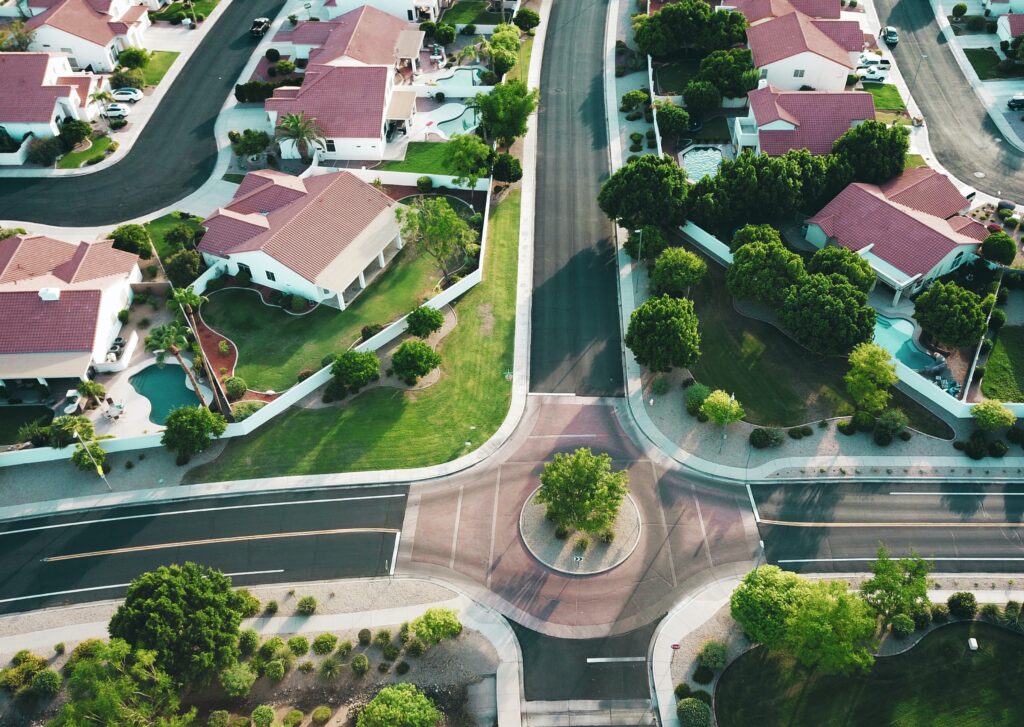
一方の自治会(町内会)はどのような団体なのでしょうか。
自治会については、任意団体であるため、加入するのは住民の意思となります。
管理組合のように強制加入ではありません。
ちなみに、横浜市における令和6年4月1日現在の例です。
会員(市民)1,205,220(前年1,213,068、前々年1,219,854/情報は掲載されていないが、筆者が継続的にカウント)世帯であり、市内全世帯の66.7%(前年67.7%、前々年68.8%)が加入しています。
すなわち、3割強は未加入で、その割合は年々増えています。
加入されていない世帯も比較的多いことが特徴的です。
昔のように地域活動が少なくなってきたことや、地域から離れて仕事にでるようになっている方が多いこと、更には共働きで自宅にいない時間が多い事情もあるように思われます。
そんな中でも、地方では伝統的なお祭りをやっている地域もあり、年間10万円以上徴収されるところもあるようです。
この記事にもある通り、自治会の意義は「防災・防犯」です。
管理組合はマンション内だけで完結です。
しかしながら、自治会はマンション内自治会とともに、周囲の関連自治会とも連携して進めていく必要があります。
町内全体でお互い協力し合える関係を築くことが、自治会の重要な視点です。
管理組合と自治会がうまく機能するためには
先ほどの判例に戻ります。
管理組合が自治会に加入することは大げさな例かもしれませんが、
管理組合と自治会は連携しながら進めていく必要が今後益々増えてくる
でしょう。
自治会における「防災・防犯」という役割は、例えばマンション全体で避難訓練を行う場合においては、区分所有者全員が加入している管理組合による協力が不可欠です。
また、住民の高齢化問題も、高齢者の安否確認や普段のコミュニケーションは自治会の役割であったり、管理組合の役割であったりするかもしれません。
滞納なく定期的に管理費・修繕積立金の回収を行っていくのは管理組合の重要な役割です。
また管理組合なのか自治会なのか、線引きが曖昧な場合もあります。
その場合はお互いに話し合いの中で解決が必要になるでしょう。
強制加入である管理組合と任意加入である自治会は、マンション住まいで普段意識されない方にとっては、どちらがどのような役割を果たしているのか、区別がつかない場合もあります。
そうなった場合には、業務をお互い融通し合いながら、解決を図るというのも方法論としてあるでしょう。
そして先ほどの判例になりますが、
「管理組合が自治会の一員となる」
というのは、一つの相互連携の在り方なのかもしれません。








コメント