2026年4月(令和8年4月)から、マンション管理の基本法である区分所有法が大幅に改正されます。今回の改正は「建替えや再生を進めやすくする」ことを目的としつつ、同時に、管理組合の運営ルールそのものを変える性格を持っています。
特に注目すべきは、「強行規定(きょうこうきてい)」と呼ばれる部分です。
この改正により、各マンションの管理規約に書かれている内容が、法律によって上書きされる場面が生じます。そのため、改正法に合わせて規約を見直さないと、総会運営や意思決定に混乱を招く恐れがあります。
今回は規約を定めても、その規約通りにはならない強行規定とともに、管理組合として対策しておきたい内容を、マンション管理士である筆者が詳しく解説します。
強行規定とは何か:管理組合が変えられない“絶対ルール”
まず初めに、強行規定とは何なのか見ておきます。
✅「強行規定(強行法規ともいう)」とは、法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに適用される規定をいう。
✅契約などによって変更することが認められている規定をいう「任意規定(任意法規)」と対になる用語
マンション管理の区分所有法に限らず、他の法律でも用いられる内容です。
具体的に、区分所有法における管理組合や区分所有者が合意で変更できる「任意規定」と、法律で強制的に適用される「強行規定」を見てみましょう。
| 区分 | 意味 | 管理組合で変更可否 | 例 |
|---|---|---|---|
| 強行規定 | 法で強制的に適用され、規約や決議で変更できない | ❌ できない | 区分所有法第31条(総会決議要件) |
| 任意規定 | 当事者の合意で変更可能 | ⭕ 可能 | 区分所有法第30条2項(議決権割合) |
強行規定に反する規約条項は、自動的に無効(失効)となります。今回の改正では、この「強行規定」に該当する条項が複数新設・修正されており、施行日に合わせて全国の管理規約の一部が効力を失うことになります。
法改正で自動的に“上書き”される主な項目
改正区分所有法では、主に総会の定足数や決議要件、再生関連の決議要件などが見直されます。
以下は、現行規約と新法施行後の対比です。
| 項目 | 改正後(令和8年4月以降) | 現行(旧規約例) | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 総会の定足数 | 議決権総数の過半数の出席 | 「半数以上」など(偶数時に差) | 区分所有法第39条第1項 |
| 特別決議の成立要件 | 出席組合員および出席議決権の各4分の3以上 | 組合員総数および議決権総数の各4分の3以上 | 区分所有法第31条第1項 ※規約の設定、変更及び廃止の場合 |
| 再生・建替え等の決議 | 組合員・議決権の各3/4以上 | 各4/5以上 | 区分所有法第62条第2項 |
| 招集通知の期間 | 原則1週間前までに発送 | 「5日以上」など | 区分所有法第35条第1項 |
これらの改正点はいずれも強行規定に基づく変更のため、令和8年4月1日時点で自動的に効力が切り替わります。
つまり、管理規約に「総数の4分の3」など旧記載が残っていても、新法の基準で総会を開けば法的に有効になります。
「改定しなくてもいい」では済まない理由
一見すると、「法律が自動で上書きしてくれるなら、規約を改定しなくてもいい」と思いがちです。確かに法的には、区分所有法の強行規定が優先適用されるため、形式的には旧規約のままでも運用可能です。
しかし、改定を怠った場合、管理組合の実務現場では次のようなトラブルが起こりやすくなります。それは単なる“文言の違い”ではなく、意思決定の混乱・信用の低下・手続上の不整合という、目に見える形で現れます。
現場での混乱
総会議案書や管理規約集に旧条文が残っていると、
「出席4分の3なのか、総数4分の3なのか」「半数と過半数の違いはあるのか」
など、ちょっとした数字の違いが総会の成立そのものを左右する事態に発展します。
このような議論は、総会の場で突発的に起こることが多く、議長や理事長が即答できずに混乱を招くケースが目立ちます。特に理事会メンバーの交代が頻繁なマンションでは、
「前任の理事長が決めたルール」「昔の総会ではこうだった」
という慣習ベースの運営が温存され、改正後の区分所有法に基づく正確な判断ができない恐れがあります。
さらに、組合員全員が区分所有法の構造(強行規定か任意規定か)を理解しているわけではありません。議事の途中で「うちの規約では4分の3と書いてある」「でも法改正で変わったのでは?」という意見が出ると、法的根拠をその場で説明できる人がいないため、議決自体が先送りになることもあります。
こうした「現場の迷い」は、管理組合のガバナンス低下にも直結します。正しいルールに基づく判断をするためにも、規約を改定して明文化しておくことが、結局は最も確実で効率的な方法と言えるでしょう。
対外的信用の低下
管理規約は、管理組合内部だけのルールではありません。不動産取引の際、買主・仲介業者・金融機関が最初にチェックする重要な書面のひとつです。
特に、令和4年以降に広がった「マンション管理計画認定制度」や「マンション管理適正評価制度」では、最新法令に適合しているかどうかが“管理水準の指標”として見られるようになっています。
仮に、管理規約が旧条文のまま放置されていると、外部からは「この組合は法改正に対応していない」「管理意識が低い」と判断される可能性があります。また、外部の調査では、管理体制の良し悪しが中古マンションの価格維持や取引価値の観点でプラス要因とされているというデータが出ています。
手続・登記の煩雑化
改正後の法制度では、裁判所・法務局・自治体が扱う手続でも「改正区分所有法の条文番号・用語」での提出が求められます。旧規約を添付資料として提出すると、「現行法との整合性を補足説明してください」「該当条文の根拠を示してください」などの追加対応が求められる場合があります。
例えば、管理組合法人の登記変更申請や、裁判所への建替え決議認可申立てを行う場合、旧条文のままだと、申請書類の整合確認に時間がかかり、結果として手続全体の遅延や修正コスト増につながります。
さらに、将来にわたって理事長や管理会社が代わると、「どの条文に基づいて決議したのか」を第三者が追跡できなくなり、法的なトレーサビリティ(証拠性)が失われてしまいます。
このようなリスクを回避するためにも、現行法対応の条文に統一しておくことが、最終的にはコスト削減につながるといえます。
改定のタイミング:総会開催日の前後で手続が変わる
改定の際は、総会開催日と施行日の関係に注意が必要です。今後の改正手続は次の2パターンに分かれます。
| 区分 | 開催日 | 適用される要件 | 効力発生日の扱い |
|---|---|---|---|
| パターン1 | 令和8年3月31日まで | 現行規約に基づく定足数・決議要件(例:総数4分の3以上) | 「施行日(令和8年4月1日)」から効力発生 |
| パターン2 | 令和8年4月1日以降 | 改正法に基づく要件(出席4分の3以上) | 決議成立時に即時効力発生 |
なお、ややこしいのですが、3月中に総会を招集しても、開催日が4月以降の場合は原則として旧法手続になります。例えば、2026年3月31日(火)に召集手続きを行い、4月18日(土)に総会を開催する場合は、旧法になる可能性があります。
新法ベースで管理規約を改定するならば、管理組合内での混乱を避けるためにも、4月1日以降に招集通知を発送することが望まれます。
管理組合として取るべき行動
具体的に管理組合としてどのような対応が必要なのか、簡単に紹介します。
自分のマンションの管理規約を確認
まず確認すべきは、「第43条(招集通知)」「第47条(総会決議)」の条文です。これらの条項は、改正区分所有法で直接影響を受ける部分です。「5日前通知」「総数4分の3」などの表記があれば、確実に改定対象です。
ただし、現時点(令和7年11月)では、実際に改定済みの管理組合はまだほとんどありません。国土交通省が改正標準管理規約を正式公表したのが令和7年10月17日であり、各組合や管理会社が内容を精査している段階だからです。
したがって、これから1年程度の間に、全国的に改定作業が本格化すると考えられます。
理事会で改定方針を検討
理事会では、次の2点を早期に決めることが重要です。
✅いつ改定するか:施行前に「予備的改定」を行うか、施行後に新法要件で改定するか。
✅誰が改定案を作るか:理事会で案をまとめるのか、マンション管理士などの外部専門家に委託するのか。
実際には、法的整合性の確認や条文表現の調整など、専門的な知識が求められます。
費用面で外部委託をためらう管理組合もありますが、誤った手続で決議が無効になった場合の損失を考えれば、1回限りの法改正対応は専門家を入れて確実に進める方が安全です。
総会では、施行日と効力発生日を明記
改定総会を令和8年3月末など、施行前に行う場合は特に注意が必要です。改定議案文中に
「この改正は令和8年4月1日から効力を発する」
と明記しておくことで、法施行後の混乱を防ぐことができます。
逆に、施行日以降に開催する場合は、決議成立と同時に効力が発生するため、改定後規約をそのまま使用可能です。また、招集通知には「改正区分所有法に基づく要件で決議する旨」を明記し、総会議事録にも新旧条文の対応表を添付しておくと、後日の確認が容易になります。
まとめ:法は自動で変わる、でも「現場」は自動では変わらない
📺 あわせて理解を深めたい関連動画
【基礎編】改正区分所有法と強行規定の全体像
強行規定とは何か、なぜ管理規約より法律が優先されるのかを整理しています。
【実務編】知らないと総会が止まる「強行規定」の落とし穴
強行規定を理解しないまま総会を進めた場合の実務上のリスクを解説しています。
改正区分所有法により、2026年4月からは強行規定が直接適用され、旧規約は失効します。管理組合としては「法が優先される」ことを理解しつつ、現場の混乱を避けるために、明文化・周知・整備を進めることが重要です。
特に、
✅総会定足数・特別決議要件の変更
✅再生・建替え決議の緩和
✅所在不明区分所有者や国内管理人などの新制度
など、日常運営にも関わる改正が多い点を忘れてはいけません。
管理規約の整備は、法対応であると同時に、管理組合の自立性を高め、資産価値を守るための第一歩でもあります。
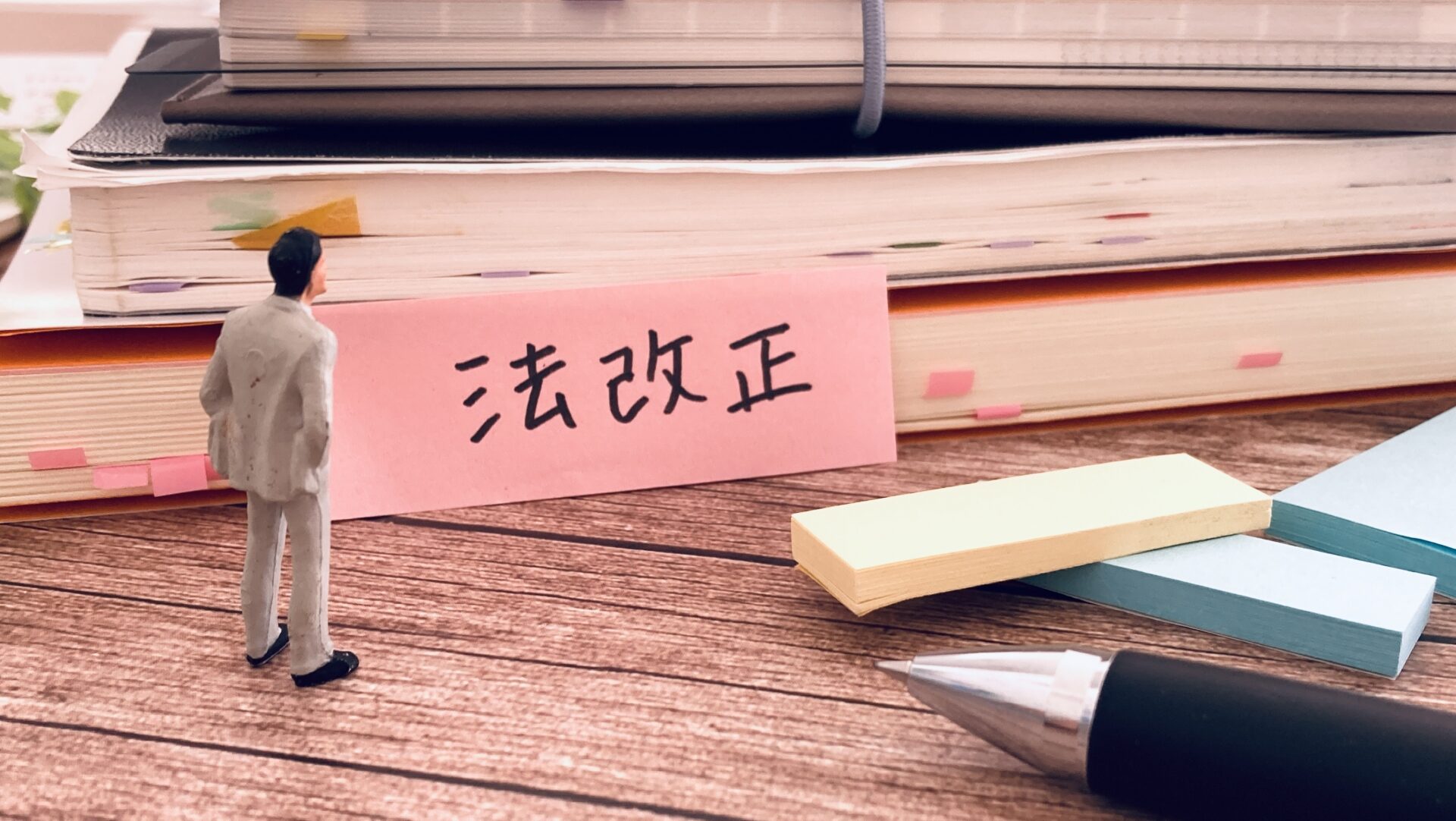






コメント
せっかく広告無効のリンクに飛んでも,依然としてサイト内別記事の紹介やイメージ画像が混在する.こういうのも記事だけを印刷したい人にとっては不要だと思う.
横浜マンション管理FP研究室です。コメントありがとうございます。
今後の運用の参考とさせて頂きます。