マンションの管理組合にとって、法定点検は避けて通れない重要な義務です。
「本当に必須なの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、結論から言えば「はい、必ず実施が必要です」ということになります。
しかし、ただ「必要」と知るだけでは不十分です。この記事では、建築基準法、消防法、水道法に基づく法定点検の具体的な内容や対応方法を、実務に精通しているマンション管理士が分かりやすく解説します。また管理組合が知っておくべきポイントを紹介していますので、最後までご確認下さい。
建築基準法に基づく法定点検とは?
まず建物の点検として、建築基準法による法定点検があります。
具体的には、次のような点検となります。
特殊建築物の定期報告とは?
特殊建築物の定期報告では、主に敷地内の地盤沈下や排水状況、基礎・外壁の構造強度などをチェックし、3年に1回、特定行政庁(例: 横浜市長)に報告します。
具体的には、以下の5項目となります。
※横浜市のダウンロード書式一覧(建築関係) 14.定期報告書式より抜粋
敷地と地盤の点検ポイント
こちらでは、
・敷地内の通路の状況
・弊や擁壁の状況
について、調査のうえ報告します。
建物外部の確認事項
こちらでは、
・外壁における防火対策
・コンクリートやタイルの劣化状況
などについて調査のうえ報告します。
屋上と屋根のチェック項目
こちらでは、
・屋根の劣化状況や防火対策の状況
・屋上にある機器や工作物の劣化状況
などについて調査のうえ報告します。
建物内部の重要ポイント
こちらの建築物の内部は、一番報告事項として多い項目ですが、
・床面における劣化や損傷状況、耐火性能等の確保状況
・天井にける劣化や損傷状況や耐火性能等の確保状況
・防火扉やシャッター等の防火設備の設置や劣化や作動の状況
・照明器具の落下防止対策
・警報設備の設置や劣化状況
などについて調査のうえ報告します。
避難施設の安全確認
こちらでは、
・廊下や出入口に物品がおかれていないか
・避難上有効なバルコニーは確保され、物品が放置されていないか、また劣化の状況
・非常階段における設置や幅員の確保や構造上適切であるか、更には劣化の状況
・排煙設備や非常用進入口
・非常用エレベーターの状況
などについて、調査のうえ報告します。
特殊建築物とは何か?
そもそも、特殊建築物とはどのような建築物を指すのでしょうか。
不特定多数の人が利用する建物であり、おもに3階以上の
・病院、診療所、ホテル、旅館、共同住宅(マンションもここに含まれる)など
・学校、体育館
・デパート、マーケット、展示場、遊技場等
などが該当します。
誰が点検を行う?資格者を解説
点検は調査資格者である、
・二級建築士
・特殊建築物等調査資格者
が担当します。そのため、区分所有者や管理会社のスタッフでは対応できないため、注意が必要です。
建築設備の定期点検とは?
こちらの建築設備定期点検報告では、おもに
・排煙設備
・非常用の照明装置
について、1年に1回点検し、特定行政庁に報告します。
地域によっては、給排水設備が対象となる事もあります。
※ちなみに東京都は給排水設備が検査対象です
具体的には、以下の通りです。
換気設備のチェック項目
こちらでは、
・中央管理方式の空気調和設備の設置や稼働の状況
・防火ダンパー等の設置状況
など、マンションに該当する部分が当てはまります。
排煙設備の確認ポイント
こちらでは、
・特別避難階段の階段室や非常用エレベーター等の排煙口や給気口
・自家発電装置の設置や稼働、性能等
など、マンションに該当する部分が当てはまります。
非常用照明の検査内容
こちらでは、
・配線や切替回路の状況
・非常用照明設備における自家用発電装置の設置や稼働状況
など、マンションに該当する部分が当てはまります。
給排水設備の点検(一部地域)
こちらは東京都の報告例ですが、
・飲料用給水タンクや貯水タンクの設置や漏水等の状況
・排水層や排水再利用配管設備、排水トラップ、通気管等の状況
など、マンションに該当する部分が当てはまります。
ちなみに、横浜市のマンションは記事更新(2025年3月22日)時点で対象外です。
誰が点検を行う?資格者を解説
こちらも有資格者のみであり、
・二級建築士
・建築設備検査資格者
が対象となります。
エレベーターの定期検査
エレベーターの稼働状況等について定期検査を行い、他の検査と同様に
1年に1回点検し、特定行政庁に報告
に報告することとなります。
また、ロープ式と油圧式で報告内容が異なりますが、おおむね
・ロープ式の場合は、巻上機の状態やロープの状態
・油圧式の場合は油圧パワーユニットの状態
・かごの内部やかごの上部の状態
・乗り場やピット(階下の機材のための空間)の状態
について、検査を行います。
この昇降機等定期検査が行うことができるのは、他の検査同様、
・2級建築士
・昇降機等検査員
の有資格者のみです。
防火設備の定期検査
マンションの防火設備に対する定期検査を行い、他の検査と同様に
1年に1回点検し、特定行政庁に報告
することとなります。
具体的には、
・防火シャッターの設置状況や劣化状態、感知器等の連動機構の稼働状況
・ドレンチャー(延焼を防ぐための外回りに設置するスプリンクラーのような防火装置)の設置状況や劣化状態、感知器等の連動機構の稼働状況
について、検査を行います。
防火設備定期検査ができるのは、
・2級建築士
・防火設備検査員
の有資格者のみです。
消防法が求める法定点検の内容
続いて、消防法によるマンションの法定点検についてです。
半年に1度または1年に1度、所轄の消防署に報告することとなります。
そして、マンションは消防法による法定点検の対象であり、1,000㎡未満であれば、
以下に記載する有資格者でなくても、マンションの防火管理者も可能です。
ただし、一般的には専門家でもある有資格者によって検査を行うことで、
安全性を担保することが求められるでしょう。
また、具体的な報告内容としては、
・屋内消火栓設備の状況
・スプリンクラー設備の状況
・泡消火設備の状況
・屋外消火栓設備の状況
・自動火災報知設備の状況
・ガス漏れ火災警報設備の状況
・避難器具の状況
・誘導灯及び誘導標識の状況
・消防用水の状況
など、消防に関する機器や設備全般を検査します。
1年に1回の報告義務があるもの:消防用設備を動作させたり、使用することによる総合点検
となります。
また、消防法による法定点検ができるのは、
・消防設備点検資格者
の有資格者のみです。
水道法に基づく水質・設備点検
最後に、水道法による法定点検についてです。
こちらは、1年に1度、水質検査報告として保健所に提出するものです。
具体的には、
・簡易専用水道管理状況検査
がマンションの規模や設備によって必要になります。
専用水道の水質検査とは?
専用水道とは、横浜市のホームページ(詳細は専用水道の手引き)の記載には、
居住人口が101人以上で水源が上水道または地下水等
であり、口径25mm以上、導管全長1,500m超
または、受水槽の有効容量10㎥超(6面点検できるものは除く)
とあります。
大規模マンションなどでこれらを満たすものが該当することとなります。
その場合において、
を実施し、速やかに所轄の保健所に報告する必要があります。
簡易専用水道の管理点検
簡易専用水道とは、神奈川県のホームページに記載には、
受水槽の有効容量が10㎥を超えるものは、
水質及び受水槽の点検、貯水槽にかかる水質異常発生時の対応を行うこと
とあり、さらには、
年に1回以上、簡易専用水道検査機関での検査を受けなければならない
ということになっています。
法定点検を怠るとどうなる?罰則を解説
それぞれの点検を怠った場合の所有者における罰則は以下の通りです。
| 点検の種類 | 点検を怠った場合の罰則 |
| 建築基準法による法定点検 | 建築基準法第101条に基づき100万円以下の罰金 |
| 消防法による法定点検 | 消防法第44条に基づき、虚偽の報告を行った者、又は報告しなかった者は、30万円以下の罰金又は拘留 |
| 水道法による法定点検 | 水道法54条第8号に基づき100万円以下の罰金 |
点検を怠ると法令違反となり、所有者に罰則が科される可能性があるため、注意が必要です。
マンション法定点検の全体像
マンションの法定点検は、建築基準法、消防法、水道法に基づき、それぞれ異なる頻度と内容で実施が求められます。今回の内容をまとめると、以下の通りです。
| 根拠法 | 報告内容 | 頻度 | 具体的な点検報告内容 | 報告先 |
| 建築 基準法 |
特殊建築物定期報告 | 3年に1回 | 地盤、屋上、建物内部等の点検 | 特定行政庁 |
| 建築設備定期検査報告 | 1年に1回 | 換気、排煙、非常用照明装置等の点検 | 特定行政庁 | |
| 昇降機等定期検査報告 | 1年に1回 | 昇降機の稼働状況等の点検 | 特定行政庁 | |
| 防火設備定期検査報告 | 1年に1回 | 防火設備等の点検 | 特定行政庁 | |
| 消防法 | 消防用設備点検報告 | 2年に1回 | 消防設備等の点検 | 消防署 |
| 水道法 | 水質検査報告 | 1年に1回/毎月 | 受水槽、貯水槽等の点検や水質検査 | 保健所 |
ほとんどのマンションが対象となるため、管理組合は定期的な点検と報告を怠らないよう注意が必要です。
ただし、これらを自力で対応するのは現実的ではないため、専門業者への依頼が賢明です。法令遵守と安全確保のために、早めの準備を心がけましょう。
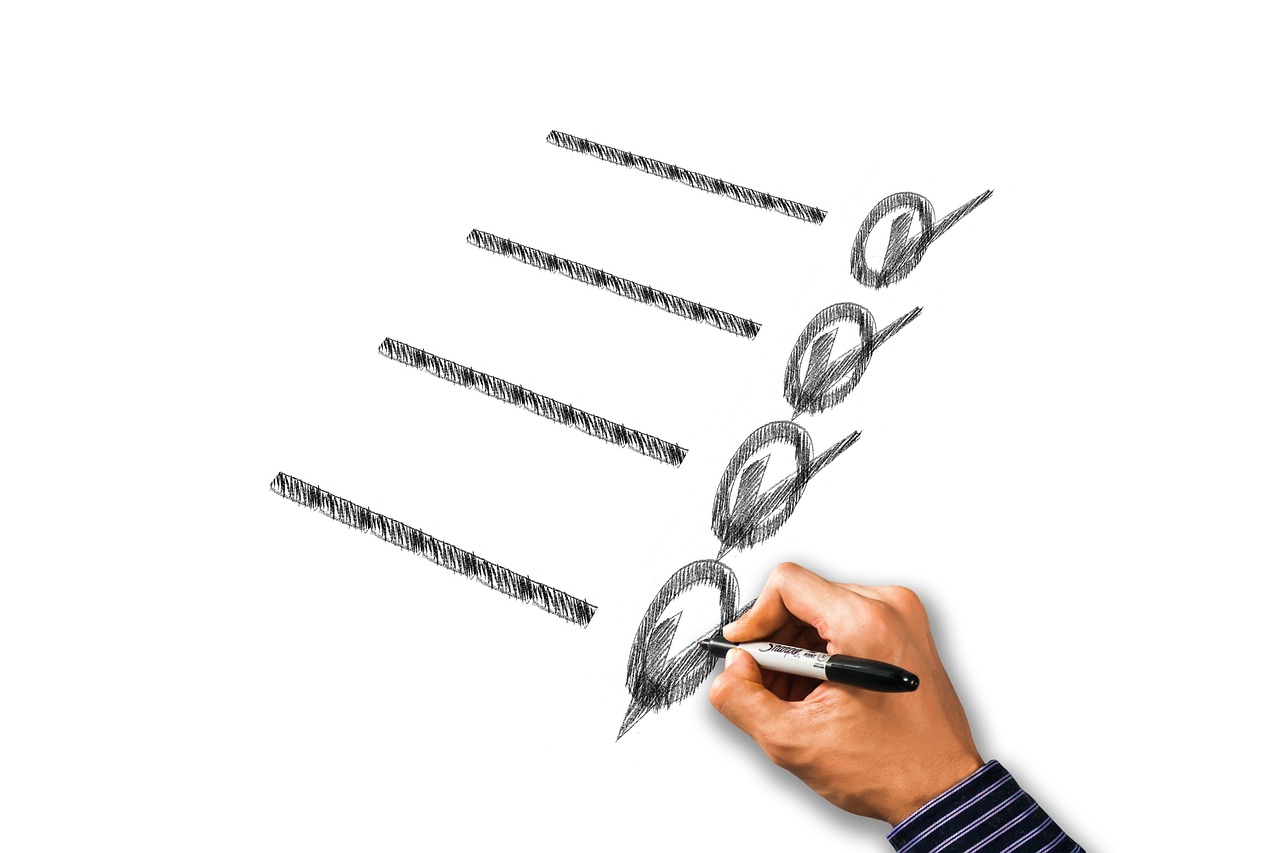




コメント