マンションを管轄する国土交通省でも、専門家の活用としてマンション管理士等を挙げていることから、マンション管理士をはじめとする専門家の活用を考えている管理組合も非常に多くあります。
管理会社がいても、外部のマンション管理士を入れた方がいい場面は確かにあります。一方で、常時の関与は過剰なケースも少なくありません。
本稿では、筆者(マンション管理士)の実務経験をもとに、どんな管理組合に“要る”のか、どんな管理組合には“要らない”のかを、マンション管理士が忖度なく整理します。
結論:マンション管理士は「要る組合・要らない組合」がはっきり分かれる
実際に筆者が見ていて率直に感じたところです。具体的には、以下の点が考えられます。
本稿の立場(忖度なし/利益相反なし)
筆者は日々、規模も課題も異なる管理組合の現場に立ち会っています。率直に言えば、外部のマンション管理士は「いつでも入れた方が良い」存在ではありません。複雑な局面では費用以上の価値を生みますが、日常運営が整い、理事会と管理会社が有機的に機能している組合にとっては“過剰な保険”になり得る――
生命保険や損害保険の存在同様に、保険という過剰な掛け金を払う可能性も考えられます。
その現実をまず共有しておきたいと思います。
判断の軸=複雑性×自走力×費用対効果
要否は三つの軸でほぼ決まります。
✅第一に複雑性。設備、対外的に締結する契約や管理規約の内容、利害関係、そして合意形成の難度がどれほど高いか。
✅第二に自走力。理事会の学習意欲や資料の標準化、記録の継続性、役員交代時の引き継ぎ体制があるか。
✅第三に費用対効果。削減・回避できるコストや、意思決定の質向上、理事の時間価値まで含めて、報酬に見合うかどうか。
複雑性が高く自走力が弱いほど「要」、逆に複雑性が低く自走力が高いほど「不要」に振れます。
3分チェック(6項目)
実務では、次の六つに“いくつ当てはまるか”を見ると早いといえます。
✅大規模修繕や主要設備更新が五年以内に迫っている
✅機械式駐車場や免震・中央監視など特殊設備を抱える
✅理事のなり手不足や役員固定化が目立つ
✅管理会社の提案比較の根拠が弱い
✅管理規約・使用細則が古いままで時代のニーズと合っていない
✅滞納や騒音・専有工事などのトラブルが増えている
このうち三つ以上なら、少なくともスポットで第三者の目を入れる価値があります。
マンション管理士の役割と限界
次に、マンション管理士のおもな役割とともに、限界について、「できること」「できないこと」として挙げてみたいと思います。
ただし、以降紹介するのは筆者が想定する場合であり、全てのマンション管理士に当てはまるとは限らない、一般的な事例として捉えて頂ければと思います。
マンション管理士ができること
マンション管理士の主戦場は「管理組合の意思決定のための設計」と「合意形成の支援」です。長期修繕計画や更新計画の妥当性を点検し、要件定義から条件書・評価表づくり、比較の枠組みまで整えることです。
管理委託仕様を磨き直し、不要な作業や二重コストをそぎ落とすことも考えられます。
また、管理規約・使用細則の改正では、条文だけでなく住民向け説明資料の整え方まで提案して伴走することもあります。
そして、第三者管理者(外部管理者)を導入するなら、管理組合の監督・評価、報酬内容・情報公開のルールを前もって設計し、運用上の揺れを止め、安定的なマンション管理状態を長期継続的に構築する。
――これらのどれも「現場が迷わず、説明できる」状態をつくる仕事です。
マンション管理士ができないこともある
一方でマンション管理士と言えども、マンションに対して万能ではありません。
訴訟代理や和解交渉といった法的代理は弁護士の領域ですし、構造・設備の設計監理や詳細な技術判断は建築士・設備の専門家が担います。
そして、フロント担当者や管理員と違い、管理会社の常駐業務を置き換える存在でもありません。
さらにいうと、どのようなマンション管理士でも得意・不得意があり、管理組合の要望を全て叶えてくれるような存在は非常に少ないと言えます。
これは前述の弁護士や建築士も同様であり、幅広い分野であるために「専門家」としての立ち位置を確立する訳であり、専門家には必ず得意分野やそうでない分野が存在します。
また、マンション管理士は、法と技術の間に横たわる“つなぎ目”を設計し、必要に応じて専門職と連携して全体を仕立てる役回りである、と理解していただくと齟齬がありません。
RACI簡易表(理事会/管理会社/管理士/区分所有者)
役割分担の原則はシンプルです。
実行部隊は管理会社、最終責任は理事会・総会です。そしてマンション管理士はその手前で協議・設計の参謀として関わり、情報公開の相手は区分所有者全員となります。
この骨格(R=管理会社/A=理事会・総会/C=マンション管理士/I=区分所有者)を崩さないことが、ガバナンスの健全性を保ちます。
ちなみに、
✅Responsible(実行):実務を手を動かして行う担当
✅Accountable(最終責任):意思決定のオーナー。承認・説明責任を負う一人(または機関)
✅Consulted(協議):意思決定前に意見を求められる関係者(双方向コミュニケーション)
✅Informed(情報共有):決定や結果の通知を受ける人(片方向)
という位置づけです。
「必要」になりやすい管理組合
具体的に、マンション管理士が必要になりやすい、または不要な管理組合に分けて見ていきましょう。
まずは必要となる管理組合からです。
大規模・複合(タワマン/団地)
住戸数が増え、附帯施設や契約が重層化するほど、入札や更新の“型”が問われます。
エレベーター、受変電、中央監視、清掃・警備・設備保守の束ね方……一つひとつは妥当でも、全体として過不足なく噛み合っているかどうかも重要です。ここで外部の目を入れると、条件の透明化が進み、理事会は“比較の土俵”で判断できるようになります。
とくにタワーマンションは、これまでの低層マンションにはなかった設備が入っていたり、大規模修繕にも特殊なスキルが必要になってきます。そして、大規模ゆえのコミュニティのあり方も考えられます。
そのため、専門的なスキルを持ち、他事例も持ち合わせているマンション管理士等の専門家がアドバイスする機会も増えてくると考えられます。
設備・管理形態が複雑(機械式駐車場・免震・中央監視 等)
複雑な設備ほど、更新時期の平準化や保守契約の束ね直し、長期的に同一の業者で良いのかの検討が効いてきます。
補助制度の適用可否や、将来コストの波をどう慣らすか――選択肢の提示と条件整理で、数年先の支出まで見通せる状態をつくるのがマンション管理士の腕の見せどころです。
小規模でも余力がある高級マンション
区分所有者者や役員の素地が高く自走力も高い。だからこそ、意思決定のスピードと役員負担の軽減を狙って、顧問として軽く伴走し、要所だけスポットで深掘りする。最小の関与で最大の効率を獲得する――
管理組合、マンション管理士のお互いにとってそんな設計が向いています。
第三者管理者方式を採用したい
理事会を置かない方式では、導入前の設計がすべてと言ってよいほど重要です。
外部管理者に対する監督指標、評価頻度、報酬の連動、情報公開の範囲。これらを契約と細則に落とし込まずに走り出すと、後から必ず管理組合内で揺れます。外部の手で“最初の型”を固める意味はここにあります。
もちろん、第三者管理者方式を採用したあとに、そのままマンション管理士が外部役員や顧問となる場合も考えられます。
追加「要」シグナル一覧
管理会社の切り替えや委託契約の全面見直しを検討している、滞納や紛争が目立ち始めた、管理規約・使用細則が時代に追いついていない――いずれも「節目に目利きを入れる」タイミングです。
管理組合としては、とりわけ「時代の流れについてきているマンション管理士かどうか」を見ていく必要があるでしょう。そうでない場合は、次章で解説するとおり、自分達で考えながらやった方がより効果的です。
「不要/自走できる」管理組合
次に、不要であったり、自分たちで自走できるタイプの管理組合を確認していきましょう。
100戸以下で費用対効果が厳しい(ただし更新期は例外)
日常運営は管理会社と理事会で十分に回ることが多く、恒常的な外部関与は割高になりがちです。例外は設備の更新期や大規模修繕工事のタイミングです。
エレベーター、配管、受水槽から直結化への転換など、一度きりだが重い意思決定や大規模修繕工事という定期的に訪れるイベントは、短期のスポットで“型”を借りるのが賢明です。
学習意欲が高く、標準化・記録化ができている
理事会や総会の議事進行の手順、総会や理事会、説明会等の説明資料の骨子、また、管理規約や使用細則の時代への対応――これらをテンプレート化し、記録を積み上げている組合は強いといえます。
役員が交代しても理事会やマンション管理全体の品質が落ちず、外部のマンション管理士等の専門家への常時関与に頼らなくて済みます。
管理会社の提案品質が高く、KPI(重要指標)がある
管理会社からの提案の根拠や指標(例えば、理事会の開催回数、区分所有者への説明回数など)が明確で、年次レビューが定着しているなら、年間を通じた顧問としてのマンション管理士の採用は不要です。むしろ、不定期的な外部からの専門家採用で十分です。
さらにKPIとして、
✅いつ、何を実施すべきかに先手を打ち、ブレがないか
✅契約内容に見合った報酬か(費用対効果にフィットしているか)
✅スケジュール管理が徹底しているか
などは重要指標として考えられます。
このような状況が確立されている管理組合は、マンション管理士の活用は第三者の“軽い健康診断”で、惰性を防ぐ程度の関与に留めればよいでしょう。
居住専門家が継続協力している
管理士や建築士、不動産実務者が居住し、継続的に助言・協力しているなら、常時の外部は不要です。利益相反への配慮だけ押さえ、必要な場面にだけ第三者の当て馬見積もりやレビューを差し込めば足ります。
オンライン活用で自走できる管理組合(読み×視聴×実践を自由に回す)
手前味噌ですが、「横浜マンション管理FP研究室」のようなマンション管理コラムやYouTube解説を含む良質な情報を、自由に読み・視聴し、そのまま会議の議題や説明資料に落とし込めている組合は、まず外部の常時関与は要りません。
根拠に基づく質疑ができ、テンプレが内製化され、記録に支えられて運営が継承されている――この循環が回っていれば、節目だけスポットで十分です。
当サイトや関連のYouTube解説も全て無料で開放しているので、是非フル活用して頂ければと思います。
マンション管理士が対応しづらい管理組合
一方で、マンション管理士側から見て、対応しずらい、または契約を見送りたい管理組合もあります。こちらは筆者視点になり、全てのマンション管理士に当てはまる訳ではないですが、具体的にはどういう特性を持つ管理組合なのか、見ていきましょう。
役員や区分所有者が高圧的・誹謗中傷発言がある
報酬を受領する以上、マンション管理士としても専門性を発揮しながら管理組合対応を行う必要があるのは当然でしょう。一方で、こちらは報酬を払っているのだからということで、高圧的な態度で出てくる管理組合も少なからず存在します。
最近ではカスタマーハラスメントという視点で、誹謗中傷を行うケースも考えられ、このような場合はマンション管理士側も疲弊することとなり、より良い関係が結びづらい状況になります。そのため、契約解除等に繋がる可能性もあります。
コンプアイアンス軽視
マンション管理運営上必要な管理規約や使用細則、区分所有法、さらには設備に関与する建築基準法、点検でも重要になる消防法などの各種法令は管理組合として遵守する必要があります。
これらの対応は、管理会社委託の場合は管理会社経由で対応することもありますが、必要なものについては、対応はマストと言えます。
一方で、管理費等の滞納で十分な資金が無いなどのやむを得ない場合を除き、対応に後ろ向きな管理組合は、マンション管理士としても関与するのを避けたくなる場合も考えられます。
極端に値切る
財政が厳しい中で管理組合としてもコストを抑えたい、しかし専門家を採用したいという考え方はあるでしょう。
一方で、専門家の採用は少なからずコストが掛かってくることが一般的です。また、提示した見積金額に対して、極端に値切ろうとすると、受け入れて貰えない可能性も考えられます。
マンション管理士も他の専門家や業者同様に、それなりに時間とコスト、手間をかけて独自スキルを構築してきています。そのため、ある程度のスキルや稼働を考えながら見積もりを提示します。費用が高いと思えば採用を見送るか、または他のマンション管理士を検討することが賢明です。
費用対効果をどう測るか
顧問契約やスポット契約等の費用はどのように考えればよいのかというのは、管理組合として頭を悩ますところです。
・管理組合としてこの金額で妥当か?
・マンション管理士がこの金額で受けてくれるのか?
の折り合いが必要となる事から、一概にいくらが良いというのは難しいと言えます。
料金レンジの目安
契約は
✅顧問(定例の軽伴走)
✅スポット(規約改正、管理会社変更、更新期支援)
✅資料作成(条件書・評価表・総会説明)
の三類型で設計すると齟齬が出にくくなります。重要なのは、回数や範囲、成果物、追加費用の条件を事前に書面で明確にしておくことです。
投資対効果の式(時間価値も明示)
実務の物差しはシンプルです。
得られる価値の合計−かかるコストの合計
具体的には、以下のように要素分解が考えられます。
左側=“得られる価値”の中身
- 削減・回避額
- 例:管理委託費の見直しで年間▲120万円、相見積で工事費を▲80万円、不要な保守契約を解約で▲20万円 → 合計▲220万円。
- 「将来のムダ払いを避けた」もここに入れます(過大仕様の回避など)。
- 入札の透明化による抑制効果
- 条件書・評価表を整えて比較可能にすると、業者は“妥当な価格”を出さざるを得ません。
- 目に見える削減までいかなくても「高止まりを防げた分」を見積もる項目です(たとえば“本来出そうとしていた見積り”と“透明化後の見積り”の差)。
- 品質向上価値
- 安かろう悪かろうを避けて故障率低下/手戻り減少などの“長期の得”を金額化。
- 例:更新後の故障減で臨時出費が年間▲30万円、清掃仕様の再設計で苦情対応が減り管理会社追加請求がなくなった等。
- 理事の時間価値
- マンション管理士が“意思決定の型”を整えることで、理事の会議準備・資料作成・業者調整の時間が減る価値。
- 金額化は「理事の時給相当 × 削減時間」でOK(例:時給2,500円×延べ120時間=30万円)。
右側=“かかるコスト”の中身
- 報酬
- 顧問料やスポット費用など、外部に払うお金。
- 内部工数の増分
- 外部を入れることで、一時的に理事側の確認作業が増える分。
- こちらも「理事の時給相当 × 追加時間」で金額化。
回収ポイント(委託費・入札競争性・保守スリム化・補助金・リスク低減)
委託仕様の磨き直しで無駄を削り、入札の競争性を確保し、保守契約を束ね直して更新時期を平準化する。そして、適用可能な補助金・助成金等の制度を拾い、事故・瑕疵・紛争の予防と早期収束で“管理組合には見えないコスト”を減らす。
この辺りは成果を数字で語りやすい領域と言えるでしょう。
導入パターン別の使い方
具体的に、導入パターン別でどのような使い方をすればよいのか、解説します。
顧問契約(軽伴走)
理事会の議題や説明資料を事前にレビューし、管理会社の提案にセカンドオピニオンを当てる。短い時間で効果を出す設計がポイントです。
スポット支援(入札・大規模修繕・規約改正・管理会社変更)
要件定義から条件書、評価表、比較、総会での説明までを一気通しで整えると、合意形成の摩擦が目に見えて下がります。専門家が客観的に間に入ることで、理事会・役員⇔他の区分所有者の摩擦や軋轢が軽減される効果を生むこととなります。
これによって、専門性を持っていない役員にとっては、余計な負担が軽減され、また、区分所有者との将来的な軋轢を生み、住みづらい管理組合になる事を避けることができます。
第三者管理者導入支援(監督・情報公開・KPI)
監督指標、評価頻度、報酬との連動、情報公開の範囲――命綱となる四点を、第三者管理者との契約と管理規約や使用細則に落とし込んで可視化する必要があります。
曖昧さを残さないことが、将来的な管理組合の安定につながります。
試用期間→成果物/KPIで続行判断
いきなり長期契約にせず、まずは三〜六カ月の“試運転”も契約によってはあるでしょう。テンプレや条件書、説明資料といった成果物、削減やスピード、満足度などのKPIで続行可否を判断すれば、最初はネガティブであったり、中立的であった区分所有者への説明も通りやすくなります。
失敗しない外部専門家の選び方
また、失敗しないようにマンション管理士や建築士等の外部専門家を選ぶにはどのようにすればよいのでしょうか。
利益相反チェック
特定ベンダーとの関係や紹介料の有無は、文書で申告を受けておきます。利益相反が発生した場合の回避措置も契約条項に入れておくと安心です。
契約の必須条項(成果物・検収・KPI・再委託・守秘)
「何回、何を、どこまで」を品目化し、検収の方法とKPIを明記すると管理組合としても納得感が高まります。もちろん、再委託の可否、守秘・個人情報の扱いも欠かせません。
提案書の比較軸(再現性・体制・透明性・実績)
“他の管理組合で発生した似た案件をどう解いたか”の事例で比べると、管理組合としての再現性・実現性が明確になります。
専門家の個人技だけに頼らず、他の違ったタイプの専門家(マンション管理士なら、建築士や弁護士等)との連携や、提案の質の向上への取組があるか、提案内容における費用の根拠が透明か――ここが将来的に管理組合に効果をもたらすこととなります。
判断フローとセルフチェック
冒頭でも紹介しましたが、改めて、マンション管理士をはじめとした顧問・専門家活用のための判断基準を紹介します。
Yes/Noフローチャート
✅大規模な設備更新・大規模修繕が五年以内にあるか
✅マンション内に特殊設備があるか
✅役員のなり手不足が顕著か
✅管理会社による提案の比較根拠が弱くないか
✅管理規約・使用細則が時代遅れで古くないか
✅滞納や騒音等のトラブルが増えていないか
――これらの分岐で「不要」「スポット」「顧問」「制度設計」のどこに当てはまるか、おおよその方向性は見えてきます。
仮に「マンション管理士不要」に振れても、年に一度の軽い外部レビューは保険として有効です。
10問チェック(該当数で推奨アクション)
そして、以下の10問の問いにも照らしてみて下さい。
✅ 設備・契約の複雑性:機械式駐車場/免震/中央監視など特殊設備、保守契約の多層化がある
✅ 入札・契約の透明性:条件書・評価表・相見積の整備度合いが十分か
✅ 規約・細則の更新状況:標準管理規約への追随や近年の改正反映ができているか
✅ 滞納・紛争の傾向:管理費等の滞納率、騒音・専有工事等の苦情が増えていないか
✅ 理事会の継続性:なり手不足や同一役員の固定化が起きていないか
✅ 主要更新の見通し:エレベーター・配管・受水槽→直結化など5年以内に更新が控えるか
✅ 住民満足度:アンケート結果や苦情件数の推移で低下が見られないか
✅ 管理会社のKPI達成度:提案の質、初回連絡までの速さ、改善提案の実行率が評価できているか
✅ 情報公開・記録の整備:議事録・資料の公開範囲と保管ルールが機能しているか
✅ 合意形成のスピード:重要議案の決定までのリードタイムが妥当か
十項目のうち、該当数が増えるほど外部の関与レベルを上げるサインだと考えてください。
FAQ
管理会社とマンション管理士の役割分担/建築士・弁護士との連携は?
管理会社は日常の実行、マンション管理士は意思決定の設計と監督補助。技術は建築士、法は弁護士。マンション管理士がファシリテーターとして横断連携し、全体を破綻なく組み立てます。
顧問かスポットか? 更新期だけ頼める?
自走力が高い組合はスポット中心で十分です。更新期は要件定義から総会説明まで“一気通し”で依頼すると、合意形成の摩擦が小さくなります。
小規模でも依頼すべき典型シーンは?
エレベーターや配管の更新、受水槽から直結化、管理会社変更、規約改正など、重くて一度きりの意思決定は外部の型が効きます。ある程度の一時的負担は発生しますが、長い目で見ると大きな効果を生む可能性があります。
費用区分(管理費か修繕積立金か)は?
運営に関わる助言は管理費、修繕・工事に密接する設計や入札設計は修繕積立金、そして設計等に関するコンサルティングは管理費・修繕積立金どちらにも対応する可能性――目的対応で整理し、事前合意を取っておくのが無難です。
第三者管理者導入時の注意点(監督・情報公開・住民理解)は?
第三者管理者は何を成果とみなすか(KPI)、いつどう評価するか、報酬への反映、どこまで情報を公開するか――全部を契約と細則に書面化する。そして、導入前に説明会を複数回開き、想定質問へのQ&A集を先出しして合意形成を進めることも重要です。
マンション管理士を使う“最適タイミング”と次の一手
マンション管理士の目は、大規模修繕・主要更新の二〜三年前、管理委託契約更新の半年前、規約の全面見直し時、そしてトラブルの兆候が早期に出たとき――この四つのタイミングで最も効きます。
マンション管理士に頼む前に、まずは当研究室コラムの様な、オープンな情報(記事・動画)で学び、理事会で小さく試してみましょう。
自走できているうちはマンション管理士は要りません。必要な節目だけスポットで相談し、意思決定の型を整える。費用対効果とガバナンスの両立は、そのシンプルな運用から生まれます。











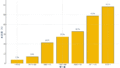
コメント