近年、私たちの身近にあるマンションが、静かに、しかし確実に深刻な課題に直面しています。それは、建物の老朽化、居住者の高齢化、そしてそれに伴う「管理不全」の進行です。管理組合の運営が行き詰まり、最終的には適切な維持管理ができなくなる「管理組合破綻」という状況は、決して他人事ではありません。
一方で、この危機を回避し、マンションという大切な資産を守るための道は必ず存在します。
本コラムでは、現在の管理不全マンションがどのような実態にあるのか、なぜ管理組合が破綻に近づいてしまうのか、そしてその危機を乗り越えるために管理組合が今すぐ取り組むべき具体的な対策について、国の調査データや自治体の事例、専門家の知見を基に、マンション管理士である筆者が詳しく解説します。
日本のマンションが直面する「二つの老い」と管理不全の深刻な現状
日本全国には700万戸を超えるマンションがあり、国民の10人に1人以上が居住しています。しかし、これらのマンションの多くが築年数を経ており、それに伴う様々な問題が顕在化しています。特に、築40年以上のマンションは2023年末で136.9万戸と全体の約2割を占め、今後10年で2倍、20年で3.4倍に増加すると予測されています(国土交通省 築40年以上のマンションストック数推移より)。
この「老い」は単に建物だけでなく、そこに住む人々にも関係しています。所有者の高齢化が進み、管理組合の役員の担い手不足が深刻化しています。役員が高齢化したり、固定化されたりすることで、新しいアイデアや活力が生まれにくくなるケースも見られます。
こうした建物の老朽化と居住者の高齢化は、「管理不全」の兆候として現れます。適切な管理が行われていないマンションは、保安上危険となるおそれのある状態、衛生上有害となるおそれのある状態、景観を著しく損なっている状態など、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす可能性が指摘されています(国土交通省 管理・修繕に関するテーマの検討資料より)。
管理状況把握と支援に向けた行政の取り組み
こうした状況に対応するため、国や自治体もマンションの管理状況を把握し、支援を行う取り組みを進めています。例えば、東京都では「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づき、管理組合がマンションの管理状況を行政に届け出る制度を開始しています。この届出制度を通じて、管理不全の兆候があるマンションを特定し、管理組合に対して必要な助言や専門家派遣による支援を行うことが目的です。
実際に、届出済みのマンションのうち管理不全の兆候があると判断された棟数が一定数存在することが報告されています。行政による専門家派遣支援では、管理規約の見直し、長期修繕計画の策定、修繕積立金の設定、管理業者の選定や変更、滞納対策など、多岐にわたる課題への対応が行われています。
また、マンションの管理計画を地方公共団体が認定する「管理計画認定制度」も導入されており、認定取得を目指す管理組合が増えることで、管理の適正化が推進される効果が期待されています。この制度を通じて、適切に管理されたマンションが増えれば、中古マンション市場の活性化にもつながる可能性があります。
なぜマンション管理組合は「破綻」の危機に瀕するのか?兆候を見逃すな!
管理不全の状態が続くと、管理組合の財政が悪化し、最終的には「破綻」に至る可能性があります。管理組合が立ち行かなくなる主な理由やその兆候を理解することは、危機回避の第一歩となります。
修繕積立金不足の構造的な問題と現実
マンションの維持管理において最も重要な要素の一つが、計画的な修繕工事を行うための修繕積立金です。しかし、NHKの報道などでも見られるように、多くのマンションでこの修繕積立金が不足しているという実態が明らかになっています。国土交通省の2023年度(令和5年度)マンション総合調査では、長期修繕計画に対して必要な積立金が「不足している」マンションの割合は36.6%に達し、5年前の調査に比べて1.8ポイント増加、さらには10年前(16.0%)から約2.3倍まで割合が増加しています。
修繕積立金が不足する原因はいくつか考えられます。
- 滞納者の増加:組合員からの積立金が滞納する。
- 工事費や人件費の高騰:物価上昇等により、当初見込みよりも修繕費用がかさむ。
- 修繕積立金の金額設定の低さ:特に分譲当初に、購入者の負担を抑えるために不適切に低く設定されているケース。
- 段階増額積立方式の採用:入居当初は低額で始まり、将来的に段階的に引き上げる方式の場合、値上げ時期に合意形成が難航したり、将来の負担が過大になったりする。
特に、1980年代以前に建てられたマンションでは均等積立方式が主流でしたが、2010年以降に建てられたマンションでは段階増額積立方式が多く採用されています。段階増額方式は、将来の値上げ幅や年齢や収入等様々な環境に置かれる組合員がいることから合意形成が難しいという問題も指摘されています。なかなか合意形成に繋がらないことによる修繕積立金の値上げの難しさ、さらには高齢者がいなくなったあとに新規入居者がいなくなることによって空室が多くなり、将来的な「スラム化」につながる危険性も示唆されています。
深刻化する管理費・修繕積立金の滞納問題
修繕積立金の不足と関連して、管理費や修繕積立金の滞納も深刻な問題です。滞納者が増えると、毎月の収入が減少し、計画通りの修繕ができなくなる恐れがあります。特に、住民の高齢化が進み、年金収入のみで生活している区分所有者が増えているマンションでは、滞納リスクが高まる可能性があります。
会計の「赤字」と「資金不足」の違い
管理組合の財政状況を把握する上で重要なのは、会計の「赤字」と「資金不足」の違いを理解することです。収支報告書上で収入よりも支出が多い状態が「赤字」です。一時的な赤字であれば問題ない場合もありますが、これが続けば資金が不足する状態(資金繰りのショート)に陥ります。
さらに注意が必要なのは、収支報告書上は「黒字」でも「資金不足」に陥る可能性があるという点です。これは、支払われるべき管理費や修繕積立金が実際に入金されていない「未収金」が長期化している場合に発生します。これは企業の「黒字倒産」と同様の状況であり、未収金が増え続ければ、必要な支払いができなくなる危機に直面します。管理組合の経理は、日々の現金の動きとは異なる「発生主義」で処理されるため、会計の仕組みを理解し、貸借対照表で未収金の状況などを把握しておくことが不可欠です。
管理会社からの「管理拒否」が意味するもの
管理不全が進行したマンションや、管理会社からの値上要請に対応できないマンションでは、管理会社から契約更新を拒否される、いわゆる「管理拒否」の事例が増えています。管理会社が管理を拒否する背景には、主に以下の理由があります。
- 人手不足と人件費の上昇:管理人や清掃スタッフといった現場人材の確保が難しくなり、人材コストが増加している。
- 収益性の低下:管理委託費の値上げ要望に応じてもらえなかったり、修繕工事を他の業者に発注されたりすることで、コストに見合う収益が得られない。
- マンションの老いとお金の面:住民の高齢化による収入減、管理費の値上げ困難、修繕積立金の不足により、管理会社の収益機会が減る。
- マンションの老いと人の面:住民の高齢化による管理組合の機能不全、役員の担い手不足、総会での合意形成の困難、モンスター住人の出現など、管理組合運営の難しさが増す。
こうした理由が複数重なることで、管理会社はビジネスとして成立しないと判断し、契約更新を辞退するに至ります。特に、「築古」で「小規模」なマンションは、修繕資金におけるスケールメリットが得られにくく、管理会社の管理拒絶対象になりやすいと言われています。「築古」でいえば、中には1981年5月以前に建築確認申請を受けた旧耐震のマンションでは、管理受託を行わないという管理会社も出てきています。
管理会社に見捨てられたマンションは、住人による自主管理を選択せざるを得ない状況に追い込まれる可能性があり、その道のりは厳しいものとなりがちです。
管理組合の機能不全と「人の問題」
管理組合の機能不全も、破綻に至る大きな要因です。役員の担い手不足や運営能力の低下により、適切な意思決定ができず、マンションが抱える課題への対応が遅れます。総会に出席者が集まらず、重要な議案の可決が困難になるケースもあります。
一方で、総会欠席者や所在不明な所有者の議決権が反対票として扱われ、とりわけ特別決議が難航する要因となっていましたが、2025年の法改正により、一定条件下で議決権の母数から除外することが可能になります。ただし、所在不明な所有者に対しては裁判所の決定が必要であり、手続きの負担は伴います。
また、一部の区分所有者による過剰な要求や理不尽なクレーム(いわゆる「モンスター」住人)も、管理会社の業務を妨げ、従業員の負担を増やし、管理拒否の要因となることがあります。これは、管理委託契約にカスハラ条項が織り込まれたことも影響しています。
「破綻」を回避し、マンションの未来を守るための具体的な対策
管理不全や破綻の危機に瀕している、あるいは将来そうなる可能性のあるマンション管理組合が、今すぐ取り組むべき対策は多岐にわたります。
長期修繕計画の策定・見直しの徹底
マンションの適切な維持管理の根幹となるのが、長期修繕計画です。国土交通省のガイドラインでは、計画期間を「30年以上」とし、「大規模修繕が2回以上含まれている」とすることが推奨されています。しかし、この計画が適切に策定されていなかったり、定期的な見直しがなされていなかったりするマンションが多く見られます。
長期修繕計画は、最低でも5年程度ごと、または大規模修繕工事のタイミングに合わせて見直す必要があります。現在の建物の状態や将来予測される劣化、そして物価や工事費の高騰を踏まえ、計画期間や修繕周期、必要な費用の積み立て額を現実的なものに見直すことが不可欠です。省エネ改修工事やマンション長寿命化促進税制の活用についても検討し、計画に盛り込むことが望ましいでしょう。
財政基盤を強化するための資金対策
修繕積立金の不足は、管理組合破綻に直結する最も大きな問題の一つです。不足している場合の対処法はいくつかあります。
- 一時金を集める:修繕費用の不足分を、区分所有者から一時金として徴収します。ただし、住民の金銭的負担が大きいため、総会での合意形成が難航する可能性があります。
- 修繕積立金の値上げを実施する:月々の積立金額を引き上げます。不足額を補填するには時間がかかりますが、長期的な資金計画を安定させる上で重要な対策です。値上げには総会での決議が必要となり、反対意見への対応や事前の説明会により合意形成を図っていく事を想定しておく必要があります。
- 足りない分を借り入れする:金融機関からの借り入れで不足分を賄います。住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」のような制度も活用できます。借り入れは住民の一時的な金銭的負担を抑えられますが、当然返済が必要であり、利息も発生するため、修繕積立金の値上げと合わせて検討することが一般的です。
- 大規模修繕の時期を変更する:建物の安全性に問題がない範囲で、大規模修繕の実施時期を後ろ倒しにするという選択肢もあります。ただし、劣化が進み、将来的に工事費用が増加するリスクも考慮する必要があります。
- 工事の内容を見直す:費用のかかる工事内容について、優先順位や仕様を見直すことも検討できます。
これらの対策を検討する際には、段階増額積立方式から、早い段階で適切な金額に引き上げて一定額を徴収し続ける「均等積立方式」への移行も有効な場合があります。国土交通省も推奨している均等積立方式は、将来の負担を平準化し、新規購入者への公平性を高める効果が期待できます。実際に、この方式への移行と大幅な値上げに成功したマンション事例も存在します。
また、滞納対策を強化することも重要です。滞納者への督促を徹底し、必要に応じて法的手段も視野に入れる必要があります。会計処理においては、管理費と修繕積立金の口座を明確に分け、区分経理を徹底することで、資金の流れを透明化し、適切な管理を行います。
管理組合運営体制の強化と外部専門家の活用
管理組合の機能不全を解消し、適切な運営を行うためには、体制強化が不可欠です。役員のなり手不足に対しては、外部専門家を活用した管理運営を検討することも有効です。例えば、マンション管理士を外部役員や第三者管理者として招聘することで、専門的な知識や経験に基づいた運営が可能になります。専門家は、管理規約の見直し、総会の開催・運営支援、管理会社との交渉、トラブル対応など、多岐にわたるサポートを提供できます。
管理の透明性を高めることも重要です。特に、管理会社との取引については、情報開示と総会での承認手続きを明確化し、定期的に報告を行うように規程を整備する必要があります。管理会社との契約内容(委託業務費、業務範囲など)を定期的に見直し、相見積もりを取るなどして、適正なコストで質の高いサービスを受けられているかを確認することも重要です。
法改正を味方につける
2025年に予定されているマンション関連の法改正は、マンション管理組合にとって重要な変化をもたらします。この法改正は、老朽化や管理不全といった課題に対処し、マンションの適切な管理と再生を促進することを目的としています。
主な変更点として、建て替えや解体、大規模な共用部分の変更といった重要事項の決議要件が緩和される点が挙げられます。特に、耐震性不足などの一定条件を満たす建て替え決議は、現行の区分所有者および議決権の5分の4以上の賛成から4分の3以上に緩和されます。また、バリアフリー化などに関する共用部分の変更に必要な賛成割合も引き下げられます。
これらの決議要件の緩和は、これまで合意形成が難航し、老朽化対策が進まなかったマンションの再生を円滑にする効果が期待されます。管理組合は、こうした法改正の内容を正確に理解し、必要に応じて専門家のアドバイスも受けながら、マンションの状況に応じた再生策(建て替え、一棟リノベーション、敷地売却事業など)の検討を進めることが重要です。
災害への備えと対策
地震や台風といった大災害への備えも、マンションの安全と管理継続のために不可欠です。マンションの耐震性や防災対策を確認し、必要であれば改修を行います。災害発生時の対応マニュアルを作成し、管理組合内で周知・共有することも重要です。既存不適格マンションに該当する場合は、敷地所有者等集会制度の活用なども検討すべきです。
まとめ:早期の対応が未来を左右する
日本のマンションは、建物の老朽化と居住者の高齢化という「二つの老い」に直面し、多くの管理組合が管理不全の危機に瀕しています。修繕積立金の不足、滞納問題、管理会社の管理拒否、管理組合の機能不全といった様々な要因が複合的に絡み合い、「管理組合破綻」という最悪のシナリオを引き起こす可能性があります。
しかし、これらの問題は適切な知識と早期の取り組みによって回避することが可能です。長期修繕計画の確実な策定と定期的な見直し、現実的な資金計画に基づいた修繕積立金の値上げや借り入れ、そして管理組合運営体制の強化は、マンションの未来を守るための必須事項です。専門家の知見を借り、2025年法改正によって緩和される決議要件なども活用しながら、マンションの再生や適切な管理の維持を目指すことが重要です。
管理不全や破綻の兆候は、会計報告書や管理会社との関係、総会の出席状況など、日々の管理組合活動の中に必ず現れます。これらの兆候を見逃さず、危機感を共有し、早期に具体的な対策に着手することこそが、マンションという大切な資産を次世代に引き継いでいくための鍵となります。管理組合員一人ひとりがこの問題意識を持ち、積極的に管理組合活動に関与することが求められています。













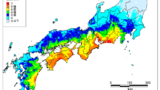


コメント