複数の業者が裏で結託し、不正に利益を分け合う「談合」はマンション修繕工事において大きな問題となっています。住民の大切な修繕積立金が狙われている可能性もあり、看過できません。今、管理組合と住民は何に気を付けるべきでしょうか。
マンションの大規模修繕工事は建物の資産価値や安全性を守るために不可欠ですが、工事業者の選定プロセスで談合と呼ばれる不正行為が起こるリスクがあります。横浜市も「マンション修繕工事で談合事件が起きています!!」と題した注意喚起を発表し、その仕組みやリスク、対策について周知を図っています。
本記事では、その背景や具体的な事例、そして管理組合が取るべき自己防衛策について、横浜市在住のマンション管理士が分かりやすく解説します。
背景:談合とは何か?その実態とリスク
談合とは、複数の工事業者が事前に話し合い、受注者や入札価格を決めてしまう不正行為です。
本来競争が働くはずの入札で裏取引があるため、工事費用が不当に吊り上げられ、工事の質も確保されない恐れがあります。これは公正な取引を阻害する違法行為であり、発覚すれば業者に行政処分や刑事罰が科される重大な問題です。
こうしたマンション修繕工事における談合疑惑は以前から指摘されており、国土交通省は2017年に一部の設計監理方式のコンサルタントが裏で特定業者に受注させるよう工作し、バックマージンを受け取っているとして注意喚起を行いました。
実際、マンション修繕工事の発注方式の約8割を占めると言われる設計監理方式では、管理組合が選任したコンサルタントが修繕計画の作成から業者選定、工事監理まで担います。本来コンサルタントは中立な立場で適正な工事を管理すべきですが、残念ながら中には特定の業者と結びつき談合を主導したり便宜を図ったりする例もあったのです。
そのような不適切なコンサルタントが関与する場合、管理組合が表向き複数社から見積もりを取っても金額は事前に調整済みとなり、適正価格の把握は極めて困難になります。また専門知識を持たない管理組合は提示された工事内容や見積もりを鵜呑みにしがちで、本当は不要な工事や割高な材料費が紛れていても気づきにくいという構造的な問題もあります。
こうした背景から、談合は長年業界の「闇」として見過ごされてきた疑いがあります。
具体例:明るみに出た談合事件
近年になり、この闇の部分が次第に明るみに出始めました。2025年3月、公正取引委員会は関東地方のマンション大規模修繕工事で約20社の主要業者が談合を繰り返していた疑いがあるとして独占禁止法違反の調査に乗り出し、一斉に立ち入り検査を行いました。
その後調査は拡大し、清水建設の子会社であるシミズ・ビルライフケアや業界大手の建装工業なども含め対象社数は30社以上にのぼったと報じられています。さらに、工事会社の選定に関与した複数の設計コンサルタント会社にも公取委が事情聴取を始めており、談合の実態解明が進められています。
こうした大規模な談合疑惑が報道されると、多くのマンション管理組合や住民に大きな衝撃を与えました。長年当たり前のように行われてきた修繕工事の裏で、これほどまで不透明な慣行が存在した可能性が浮き彫りになったからです。
「自分たちのマンションも狙われているのではないか?」と不安に感じる管理組合も少なくないでしょう。まさに決して他人事ではない問題として、警戒の声が高まっています。
管理組合が取るべき自己防衛策(横浜市より)
では、管理組合や住民は談合の被害に遭わないために具体的に何ができるのでしょうか。横浜市は談合防止のために以下の5つの対策を挙げています。ここではそれぞれのポイントをさらに深掘りし、実践のコツを解説します。
メディア等でもこれだけ騒がれているので、修繕業者や設計監理を行う建築事務所はかなり警戒していると想定されます。それでも何十年と長年続いた慣習のため、根深く残っている可能性も否定できません。大規模修繕工事を予定している管理組合として、横浜市が挙げる以下の対策は必ず実施して臨むのが良いでしょう。
管理会社推薦の業者だけでなく、複数の業者から見積もりを取得する
最初から管理会社イチ押しの1社に絞るのではなく、必ず複数の施工業者に声をかけて見積もりを取りましょう。その際、ただ形式的に数字を集めるだけでなく、各社に工事内容の詳細な説明や内訳明細を提示してもらい、納得できるまで比較検討することが重要です。
見積もり金額に大きな開きがある場合はなぜかを質問し、不自然な高値や共通した価格設定がないか注意します。複数社競合させることで業者間の緊張感も生まれ、不正な取り決めがしづらくなる効果が期待できます。
入札制度を導入し、透明性を確保する
できる限り入札(競争見積もり)の仕組みを導入し、工事契約のプロセスを透明に保ちましょう。具体的には、事前に選定基準や契約条件を明確にしたうえで複数業者に提案を募り、価格だけでなく提案内容・工法や実績も含めて総合的に評価するプロポーザル方式の採用も有効です。
プロポーザル方式であれば各社が管理組合の要望に沿ったプランを提示し、相見積もりより踏み込んだ比較検討ができます。いずれの場合も、業者が互いの見積額や提案を事前に知ることがないよう、例えば入札時に密封した形で提出させる、説明会や現地調査は別日程で個別に行う等の配慮も必要です。透明性と公平性を担保する工夫が談合の入り込む余地を減らします。
プロポーザル方式については、以下のコラム
でも詳しく紹介しています。
第三者の専門家(マンション管理士・建築士等)に相談する
管理組合だけで判断が難しい場合、第三者の専門家の力を借りることも検討してください。マンション管理士(一級建築士事務所を持つコンサルタントなど)に顧問的に関わってもらい、修繕計画や見積もり内容をチェックしてもらうのです。
実際、横浜市だけでなく各自治体はマンション管理組合向けに修繕工事の見積りが適正か相談できる窓口や専門家派遣制度を用意しています。ただし専門家であれば誰でもよい訳ではなく、依頼するコンサルタントの経歴や実績、透明性をよく調べ、特定業者と癒着していないかにも留意しましょう。必要に応じて複数の専門家から意見を聞き比べることも大切です。
外部のプロに一定の費用は掛かりますが、管理会社とは独立した立場でチェックを受けることで、結果的に無駄のない適正な工事につながり長期的には節約になる可能性もあります。
また、手前味噌ですが、他のコラム含めた、横浜マンション管理FP研究室のコラムを読んで頂くと、専門家に頼らなくても一次対策としてマンション管理組合でも動けるよう、できるだけ工夫して書いています。各コラムのタイトル横にある「サイト内検索」でキーワードを入れて頂くと、関連記事が複数出てきます。
現時点ではすべての記事が無料で読めるようになっているので、管理組合の一次対策として、有効に機能すると考えています。
業者選定の過程を記録・共有する
どのように候補業者をリストアップし、何を基準に選定したのか、その過程を文書に記録しておきましょう。また理事会や修繕委員会内だけでなく、その情報を組合員(住民)ともできる限り共有し、オープンに進める姿勢が大切です。
情報公開と透明性の確保こそが不正抑止の第一歩です。仮に誰かが不当な働きかけをしても、記録が残り多数の目に触れる状況では発覚しやすくなります。住民全体で経過を見守ることで、「おかしいぞ」と思った時に声を上げやすい雰囲気づくりにもつながります。
契約に違約金条項を設定する
修繕工事の請負契約を結ぶ際、談合など不正行為が発覚した場合に契約を解除できることや、損害賠償として違約金を請求できることを契約書に盛り込んでおきましょう。国土交通省もマンション修繕工事の契約における談合防止のための違約金特約条項の整備を各団体に通知(マンション修繕工事に係る請負契約における談合違約金特約条項について)しており、契約条文のひな型を提示しています。
違約金の設定にあたっては専門家(弁護士等)に相談することが望ましく、横浜市でも専門家(弁護士)が登録された相談制度を案内しています。万一不正が明るみに出た際に備える意味でも、契約段階でリスクヘッジしておくことが管理組合の責務と言えます。
まとめ:透明性と警戒心がマンションを守る鍵
今回明らかになった修繕工事を巡る談合疑惑は、マンション管理の世界に長年横たわる課題を浮き彫りにしました。管理組合としては「自分たちは大丈夫」と油断せず、常に疑問を持ち積極的に情報収集し、上記のような対策を講じていくことが肝要です。
透明性の高い業者選定と厳格な工事監理を徹底することで、談合の再発防止と大切な資産の防衛につなげていかなければなりません。万一不審な動きを感じたら、些細なことでも臆せず声を上げ、然るべき対応を取りましょう。「談合の餌食にはさせない」という強い姿勢で臨むことが、悪質業者への何よりの抑止力になります。
また、今回の事件を契機に業界全体でもチェック体制の強化や意識改革が期待されています。公取委の調査が進み、違反企業への処分が下されれば業界のコンプライアンス意識も高まるでしょう。
しかし最終的にマンションを守るのは現場である管理組合と組合員自身です。適正で健全な修繕工事を実現するために、今後もアンテナを高く張り、知識と防衛策を持って立ち向かいましょう。
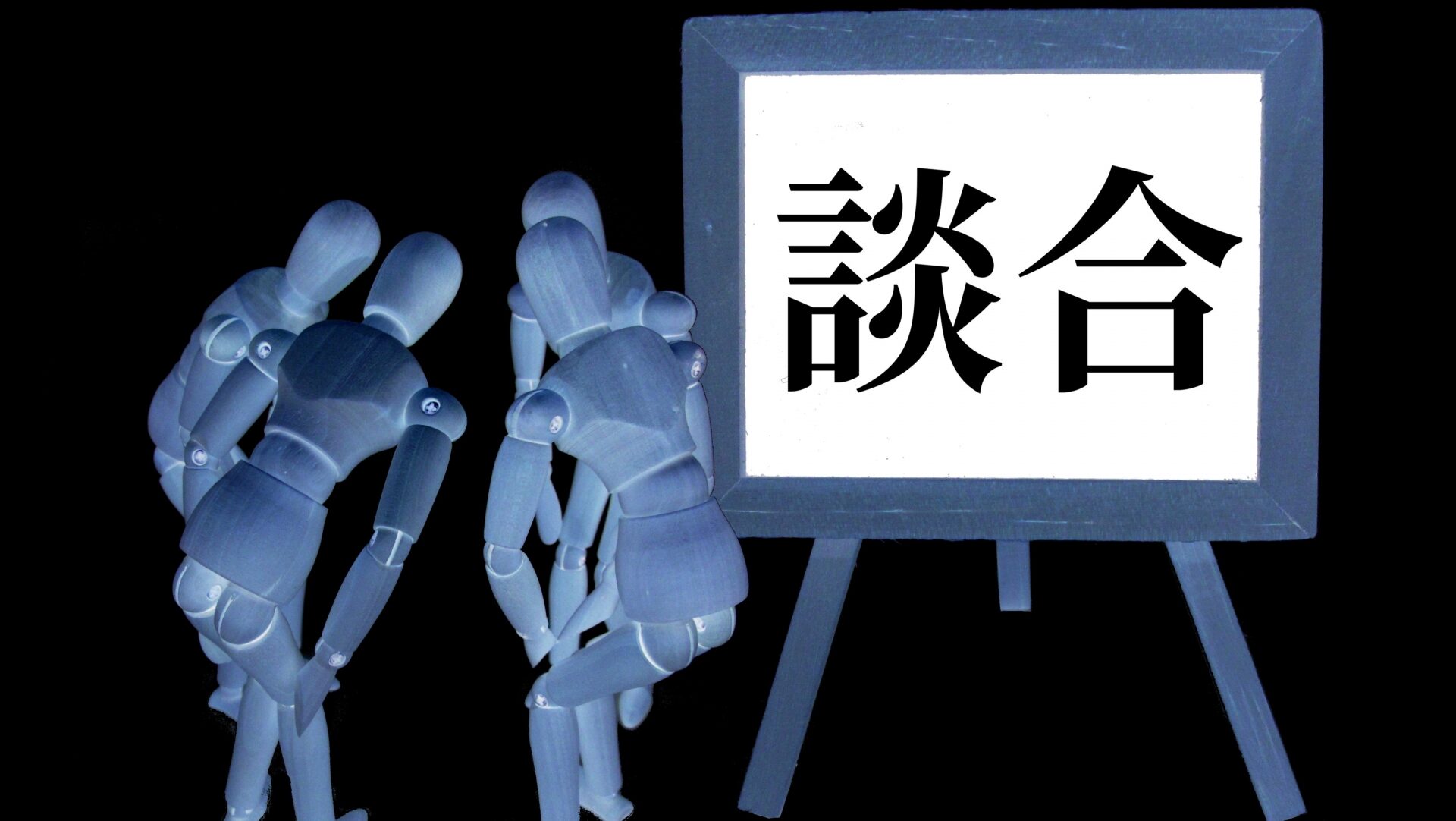
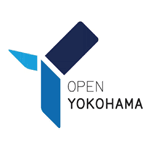



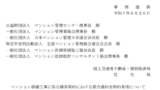


コメント