長引く低金利時代が転換期を迎え、住宅ローン金利の上昇が現実味を帯びてきました。最近では、住宅ローンの返済が60代・70代まで続くケースも珍しくありません。住宅金融支援機構の調査によれば、住宅ローン利用者の平均借入時年齢はマンション購入で約40歳前後となっており、35年ローンを組めば完済時は70歳半ばに達します。実際、70代では手取り収入の約4割が住宅ローン返済に消える可能性があるとの試算も報じられています。
本記事では、マンション管理士でもあるFP(ファイナンシャルプランナー)の視点を交え、住宅ローン金利上昇による老後のリスクと、安心して暮らすための備えについて考えてみます。
住宅ローン返済が60代・70代まで続く時代のリスク
定年後も続く住宅ローン返済の現実
「定年前に住宅ローンを完済したい」と考える方は多いですが、現実には定年後も返済が残る世帯が増えています。株式会社野村資本市場研究所の調査では、60~64歳の世帯の約19.5%、65~69歳でも約12.9%の世帯が何らかの住宅ローン債務を抱えていました。40代以降になって住宅ローンを借りる人が増え、完済が70代以降にずれ込む傾向が強まっているのです。
こうした中、専門家は「40代以降で借りた人の多くは70代以降も返済が続く可能性があり、リストラや介護など予期せぬ事態が起これば住宅ローン破綻に陥る人が増えかねない」と警鐘を鳴らしています。
収入が減る老後に住宅ローンを抱えることは、家計に大きな不安材料となります。
金利上昇で膨らむ老後の返済負担
長らく低水準だった住宅ローン金利も上昇局面に入っています。日本銀行は2024年にマイナス金利を解除し、同年7月には政策金利を0.25%引き上げました。これに伴い、大手銀行の変動金利型住宅ローンも金利がじわり上昇しています。変動金利型では「5年ルール」(金利が上がっても5年間は月々返済額が据え置かれるルール)があるため一見安心に思えますが、その間に利息の負担が増え、結局5年後以降に返済額が跳ね上がるリスクがあります。
特に注意すべきは、老後の収入減少と金利上昇が重なることによる返済負担の増大です。例えば可処分所得(手取り収入)は一般的に40代をピークに、その後大幅に減少します。平均的なケースでは、40代で月約61万円あった可処分所得が、70代では月約42万円まで落ち込む一方で、同じローン返済額が金利上昇によって月15万円から16万円、さらにはそれ以上に増える可能性があります。
その結果、70代では手取りの3~4割が住宅ローン返済に消える計算になり、生活を圧迫しかねません。老後の限られた収入から高額のローン返済を続けることは、日々の生活費や医療費などにも支障をきたす恐れがあります。
さらにマンションの場合、管理費や修繕積立金といった維持費も加齢とともに負担が増す点に注意が必要です。国土交通省の調査によれば、新築時と比較した最終計画年の修繕積立金平均額は約3.58倍に増額されており、たとえば月5,000円だった積立金が30年後には18,000円以上になるケースも珍しくありません。
加えて、職人の人件費や材料費の高騰もあり、大規模修繕工事をはじめとしたマンション共用部分の修繕費用も年々上がることが想定されます。ローン返済が残る中で、このようなマンション維持費の値上がりが重なると、老後の家計に一層重い負担となるでしょう。
老後に住宅ローンが及ぼす主なリスク(要点整理):
- 収入減と返済負担増: 定年退職後は給与収入が年金収入などに減少し、可処分所得が大きく目減りします。その中でローン返済が続けば、現役時代以上に返済負担率が高まります。
- 金利上昇リスク: 変動金利型ローンでは将来の金利上昇により月々返済額や総返済額が増加します。金利上昇は長期間にわたり家計を直撃し、返済計画を狂わせる要因です。
- 健康リスクと収入途絶: 病気や介護などで働けなくなったり、会社の早期退職・リストラに遭ったりすると、予定していた収入が得られずローン返済が困難になる恐れがあります。高齢になるほどこのリスクは高まります。
- マンション維持費の増加: 年数経過に伴い、管理費・修繕積立金が年々値上がりしたり、大規模修繕で一時金の徴収が発生するリスクもゼロではありません。老後の固定費負担が想定以上に増える可能性があります。
- 資産価値や売却リスク: 万一ローンを返せなくなって売却を検討しても、高齢期のマンションは資産価値が下がり売却益がローン残債に満たないリスクがあります。リバースモーゲージ等の活用も物件や条件によっては難しいことがあります。
無理のない返済計画と将来への備え
上記のようなリスクを踏まえ、住宅ローンを組む段階から無理のない返済計画を立てることが肝心です。具体的には、完済時の年齢と老後の収支を見据えて借入額・返済期間を設定しましょう。銀行の審査上は完済時年齢が80歳程度まで認められるケースもありますが、可能なら60代前半~65歳までに完済できる計画が望ましいです。定年時にローン残高が大きく残らないよう、返済期間の短縮や繰上げ返済の活用も検討しましょう。
また、借入時には将来の金利変動も考慮に入れる必要があります。変動金利の低さは魅力ですが、金利上昇リスクに備えて金利タイプの選択も戦略的に行いましょう。例えば、一定期間だけ固定金利にするミックスローンや、金利が上がり始めたら固定に借り換える方法もあります。将来の金利シミュレーションを行い、金利が1~2%上昇した場合でも家計が耐えられるか検証しておくと安心です。
借入当初の返済負担率が高すぎる場合は、物件価格の見直しや頭金の増額も含め再検討することをおすすめします。ローン返済額の目安として、現役時代の手取り収入に対する返済割合は25%程度までに収め、退職後に収入が減った場合でも家計を圧迫しすぎない水準にとどめるのが理想です。
さらに、マンション購入前には物件の管理状況や将来の維持費も確認しておきましょう。管理費・修繕積立金の将来計画を把握し、老後に大幅な値上げが予定されていないかチェックすることも大切です。とりわけ、マンションの長期修繕計画を入手し、将来的な支出予想を考えていく事は購入者にとっては必要不可欠です。
仮に値上げ予定がある場合でも、その時期までにローンを繰り上げ返済して負担を減らせるよう計画するなど、トータルな視点でマネープランを立てましょう。物件の「安さ」「今が買い時」など目先のメリットに注目するだけではなく、終の棲家とするのであれば長期的な視点から、マンション管理組合の計画性も見ていく事が非常に重要であると言えます。
老後も安心して暮らすための「残債対策5カ条」
最後に、ファイナンシャルプランナー(1級ファイナンシャル・プランニング技能士/FP1級)とマンション管理士の視点から、住宅ローンの残債に備えるための5つのポイントを箇条書きで整理します。将来にわたって安心な家計を維持するために、ぜひ参考にしてください。
その1:35年ローンは「猶予期間」と心得る
ローン契約時に「返済期間は最大で35年あるから大丈夫」と油断せず、35年という期間は将来に備えるための猶予期間と考えましょう。実際、「35年ローンは余裕ではなく猶予である」との指摘もあります。この間に家計のムダを見直し、繰上げ返済や貯蓄・資産運用に努めて、老後までに少しでも負担を減らす計画を立てることが重要です。
その2:低金利の今こそ余裕資金を貯蓄・資産運用に回す
現在の低金利環境下では返済額に余裕が出やすいですが、その“浮いた分”を浪費せず将来のために貯蓄や資産運用に充てることが肝心です。金利が上がればいずれ返済額も増える可能性が高いため、今のうちに資金を蓄え、資産運用で資金を増やしておけば、将来の金利上昇や緊急時にも備えられます。例えば、毎月2~3万円を積立投資に回せば、複利効果で老後の心強い蓄えとなるでしょう。
特に筆者としてのお勧めなのは、税制面でもかなり優遇があるNISAとiDeCoです。余剰資金の運用方法としては、リスク許容度を見ながらまずは手掛けたい運用方法と言えます。とりわけ、iDeCoは将来の年金の足しには最適な運用手法といえ、早ければ早いほど複利の効果を発揮する可能性があります。
その3:健康管理で60代・70代も働ける体力づくり
老後の家計を支える上で、自らの健康と体力は最大の資本です。定年後も元気で働けるよう、日頃から健康管理を心がけましょう。幸い現在は企業の定年延長や再雇用制度の整備が進み、希望すれば65歳以降も働ける環境が整いつつあります。健康であれば、60代・70代でも収入を得ながら住宅ローンを返済し続ける選択肢が持てますし、公的年金の繰下げ受給(受給開始を遅らせる代わりに月額を増やす制度)などもうまく活用できます。
仮に、繰り下げ需給の場合、1カ月の繰り下げで0.7%分増額されることから、65歳の年金を5年繰り下げて70歳から受給するとすると、仮に65歳時点で15万円/月の年金受給額であれば、
✅増額割合:5年×12か月×0.7%=42%
✅年金受給額:15万円/月×(100+42)%=15×1.42=21.3万円/月
さらに、75歳まで繰り下げると、
✅増額割合:10年×12か月×0.7%=84%
✅年金受給額:15万円/月×(100+84)%=15×1.84=27.6万円/月
と大幅に増加する計算になります。
逆に健康を損なうと働けなくなり計画が崩れてしまうため、「人生100年時代」を見据えた体調管理が欠かせません。
その4:繰上げ返済は緊急資金を確保してから
「借金を一日でも早く返済したい」と多くの人が考えることから、まとまった資金ができたら繰上げ返済で残債の解消や利息軽減を図りたくなります。しかしながら、手元資金が枯渇すると普段の生活に支障をきたすことにもなりかねません。繰上げ返済は手元資金に十分な余裕がある場合に限り行うのが鉄則です。目安として、少なくとも半年~1年分の生活費は緊急予備資金として確保しておきましょう。
急な病気や失業など予測不能の事態が起こっても、生活費の蓄えがあればローン返済の延滞を防げます。繰り返しですが、繰上げ返済を急ぐあまり預貯金まで使い切ってしまうと、いざという時に身動きが取れなくなります。「余裕資金で計画的に繰上げ返済」が賢明なスタンスです。また、繰上げ返済のしすぎで教育資金や老後資金が不足しては本末転倒ですので、ライフイベント全体を見据えバランス良く資金配分しましょう。
ローンの残債と、日々の生活のための手元資金のバランスを考えると、ローンが残り続けることが必ずしも悪ではないという点も考えておく必要があります。
その5:退職金頼みの完済計画は危険
「ローン残高は退職金で一括返済すればいい」と考えるのは危険です。平均寿命が伸び90歳近くまで生きる時代では、退職金は老後資金の貴重な原資です。その大半を住宅ローン返済に充ててしまうと、退職後の生活資金が不足し、老後破産につながりかねません。
実際、退職金をつぎ込んだ結果、年金だけでは生活が成り立たず困窮するシニア世帯も見受けられます。退職金は医療費や介護費など予測不能な支出にも備えつつ、一部を繰上げ返済に充当するにとどめるなど、老後資金とローン返済のバランスを取ることが大切です。必要であればFPに相談し、退職金の使い方も含めた資金計画を立てましょう。
おわりに:安心できるマネープランで豊かな老後を
住宅ローンの完済が60代・70代に及ぶリスクと、その備えについて解説してきました。金利上昇時代においては、将来を見据えた慎重な資金計画とリスク管理がこれまで以上に求められます。ポイントは「早めの対策」と「計画的な備え」です。ローンを組む段階から老後までのシミュレーションを行い、無理のない返済計画と十分な蓄えを用意しておきましょう。
幸い、正しい知識と計画があれば、住宅ローンが人生の重荷になりすぎる事態は避けられます。マイホームは「人生を豊かにする場」であるべきで、そのためには資金面の安心が不可欠です。将来にわたって住まいと人生を守るために、ぜひ本記事の内容を参考にしていただき、余裕を持った家計設計につなげてください。堅実なマネープランで備えを万全にし、マンションライフを心から楽しめる豊かな老後を実現しましょう。






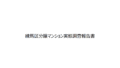
コメント