上越新幹線の駅から徒歩圏に林立する越後湯沢のリゾートマンション(以下、RM)。マンション管理センターが発行する「マンション管理センター通信」2025年10月号において、越後湯沢の事例に基づけば、2025年3月末時点でRMの定住者は約1,770人、町人口に占めるRM定住者の比率は約22%、定住層の高齢化率は47%に達しています。
加えて、非定住オーナーのうち「年1回も利用しない」層が一定割合存在し、管理費・修繕積立金の確保や大規模修繕の合意形成に波紋を及ぼしていることが示されています(以上はいずれも誌面情報より引用)。
本稿では、このファクトを出発点に、公開資料から得られる客観データを照合しながら、RMが直面する構造的課題と、管理組合および自治体が取り得る現実的な選択肢を整理します。
画像:Victoriatower-yuzawa-202107.jpg
撮影者:大澤太太郎
出典:Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Victoriatower-yuzawa-202107.jpg
ライセンス:CC BY-SA 4.0
越後湯沢で何が起きているのか(供給の起点と2020年代の反転)
1980〜90年代初頭のスキーブームに牽引され、越後湯沢では多数のRMが供給されました。バブル崩壊後は価格下落や未利用化が進みましたが、近年は二地域居住やテレワーク、インバウンド回復を背景に再評価の兆しがあります。
住宅・不動産情報プラットフォームLIFULLによる分析では、越後湯沢の中古マンション掲載価格は2019年比で約1.68倍(107万円/坪→181万円/坪)まで上昇したと報告されています。反響(問い合わせ)も増加傾向で、中心ストックの築年は平均38年、すなわちバブル期供給の物件群が主役です。
一方、現地ルポでは町の人口動態に「社会増」の年が続いた事実が観察され、RMを含む住まい方の変化が、観光中心の町の生活圏にも影響を広げ始めていることが指摘されています。
定住化の実像—「22%」「1,770人」「47%」が意味するもの
「マンション管理センター通信」2025年10月号によれば、2025年3月末時点でRM定住者は約1,770人、町人口比で約22%。定住層の高齢化率は47%で、町全体の高齢化率38%(資料記載による)を上回る水準です。
誌面に掲載されていた学術研究でも、湯沢町役場への聞き取りや住民票異動データを基に、2010年代以降にRMへの住民登録が増えた経緯が整理されています(日本建築学会北陸支部研究報告集による、新潟県湯沢町におけるリゾートマンション定住化の実態に関する研究データ。直接ダウンロードになりますので必要に応じてご参照ください)。
数の裏にある生活像を読み解くと、
①駅近物件を中心に日常利便性が向上し通年居住が成立しやすい
②管理良好な棟では医療・買物アクセスや除雪体制など生活インフラの説明が入居判断に直結している
③一方で高齢単身・夫婦のみ世帯の割合が高く、冬期対応・ごみ出し・荷物運搬・除雪支援など「生活支援の制度化」が喫緊、
という三点が浮かび上がります。
非定住オーナーの「未利用化」と合意形成の壁
マンション管理センターの記事では、非定住オーナーのうち年1回も利用しない層の存在、短期滞在中心の層が多数派である状況、そして「管理費・修繕積立金の確実な徴収」「大規模修繕の意思決定」「老朽化設備の更新」を巡る難しさが挙げられています。
とりわけ築30〜40年超の棟では、給排水・外壁・機械式設備・温浴施設など更新費用が重く、遠隔オーナー比率が高いほど合意形成が遅れがちになります。自治体計画(湯沢町観光振興計画2024年改定)でも、RM利用者を含む移動・二次交通の改善、インフォメーション機能の強化が課題に掲げられており、居住・滞在の双方に跨るインフラ整備が町の政策テーマになっていることが、この資料からも確認できます。
価格は回復しても「管理」は別問題—熱海等の比較
価格トレンドだけを見ると、首都圏近郊の温泉リゾートである熱海市でも前述したLIFULLのデータによれば、中古マンション掲載価格は2019年比で約1.09倍(2,001万→2,171万円)、エリア全体では中古物件が約1.15倍へ上昇とされます。
しかし、熱海市の住生活基本計画は、温泉・プール等の共用施設をもつRMは所有者属性が多様で管理更新が難しい、投資対象化で低利用の懸念がある、と課題認識を明記しています(熱海市住生活基本計画)。すなわち「価格回復≠管理の安定」であり、管理水準と合意形成力をいかに確保するかが、RM再評価局面の最大のボトルネックです。
他地域の知見—軽井沢にみる二地域居住と通勤圏化
リゾートの定住化は越後湯沢に限りません。軽井沢では北陸新幹線開業後、東京圏からの移住が進み、とくに西部の追分地区で現役世代の移住が顕著とする研究が報告されています。
新幹線通勤やテレワークを組み合わせる「アメニティ移住」が、教育・子育て環境や居住環境の質を重視する意思決定と結びついているとされます(J-STAGE 軽井沢町およびその周辺の新興別荘地区における現役世代のアメニティ移住)。RMという箱に限定せず、広義の「別荘・二地域居住」を含めた居住形態の多様化が、観光地の定住人口や生活サービスの需要構造を変えつつある点は、越後湯沢とも地続きの示唆です。
管理組合がいま講じうる現実的手当
RMによっては機能しづらい点もありますが、管理組合としてどのような手立てを打っておくべきなのか、マンション管理士の視点から取り組んでおきたい3点の切り口を紹介します。
第一に、未利用住戸の「見える化」と督促フローの平準化です。総会資料での稼働率推移や使用状況の可視化、Web口座振替・リマインドの電子化、弁済計画の個別合意など、遠隔オーナー前提の回収フローへの転換が不可欠でしょう。
第二に、大規模修繕の合意形成を早期化する「方針→概算→修繕積立金の早期修正」の三段階提示が挙げられます。将来像と費用水準のラフを先出しし、長期修繕計画に沿って積立金単価を段階的に見直すことが重要です。もちろん、「段階的」ではなく、国土交通省も推奨している「均等」になるような積立方式が望まれますが、足らない金額が大きくなると、反対する区分所有者が相応に出ることも想定されるため、「段階(増額方式)」の視点から入ることが望まれます。
第三に、生活支援の外部連携です。冬期支援・荷物運搬・家事代行・ドアtoドア交通などの地域サービスと接続し、「住めるRM」への転換コストを最小化します。
第四に、共用設備は「選択と集中」の視点を取り入れることも考えられます。温浴・プール等の高コスト設備は、保全レベルの再定義や休止・転用の可能性も含め、ライフサイクル費用に照らして合意を取ります。これらは法令改正や補助金の有無に左右されにくい、現場主導の打ち手として有効と言えるでしょう。
自治体・広域の役割—交通・情報・居住支援の三位一体
湯沢町の観光振興計画は、RM利用者を利用者像に含め、二次交通の整備や案内機能の改善を掲げています。定住・長期滞在が増える局面では、路線バスの利便性、キャッシュレス、駅・病院・大型店のアクセシビリティは生活基盤そのものです。
また、熱海市の計画が示すように、リゾート地のRMは所有者属性が多様で管理が難しい—この共通課題に対し、地域包括支援センターや社会福祉協議会と連携した高齢世帯支援、未利用住戸の流通促進(民泊ではなく中期賃貸を含む)等、住宅政策と観光政策を接続する枠組みが不可欠です。
中古流通の現在地—「築40年超」と取引の厚み
公開データの全数把握は難しいものの、越後湯沢の中古市場では築40年前後の物件が流通の中心にあり、価格水準の回復は主に駅近や積立・管理状態の良い棟に先行して表れています。
前掲の価格指標(LIFULL、2019→2025年で坪単価107→181万円)自体はエリア全体の掲載データに由来し、個別の管理・修繕履歴を反映しきれません。ゆえに管理の「見える化」と情報の一体提示(長期修繕計画、積立残高、共用設備の更新履歴)は、今後の適正売買に不可欠と言えます。
二地域居住という大きな潮流—ニセコの経験から
さらに、最近外国人に大変人気があり、価格高騰が著しい北海道ニセコでは、訪日客の長期滞在と住民化が進み、教育や決済など生活インフラの国際対応が自治体課題として顕在化したことが報告されています(日本交通公社 滞在型リゾート「ニセコエリア」の現状と課題)。
価値観やルールの前提が多様化すると、地域の合意形成は従来の延長では機能しにくくなる—この知見は、国際観光と関係人口の拡大を狙う各リゾート地にとって示唆的です。
越後湯沢でも、インバウンド回復と新幹線による首都圏近接性を踏まえると、二地域居住や長期滞在が増えるほど、居住・観光・投資の境界をまたぐルールの整備が重要になります。
比較データ—熱海の別荘所有者アンケートにみる利用頻度
静岡県熱海市が2024年度に実施した別荘所有者アンケートでは、来訪頻度の平均は年14.2回、1回あたりの滞在日数は平均3.3日という結果が示されました。(次期 熱海市観光基本計画の策定 第1回 熱海市観光戦略会議 資料 2025(令和7)年8月22日 95ページ・資料96枚目)
別荘という事で、戸建ても含めたものではありますが、年間365日のうち、月1回以上訪問し、約47日を熱海の別荘で過ごすというイメージです。RM所有者もいる中で、その方が管理組合活動にどれぐらい力を入れているのかというのは、推測が難しい点もあります。そもそも余暇で来ている方が多い中で、負担の多い管理組合活動にどれだけ力が入るのかという点も課題としてありそうです。
また、毎週訪れる層も一定数存在します。RMと別荘のストック構成は異なるものの、「二地域居住・リピート滞在が生活圏に与える負荷・便益」を定量把握し、交通やゴミ、医療へのアクセスを設計していく必要性は、越後湯沢にも共通する論点と言えそうです。
結び—「住める」かどうかが資産価値を分ける
越後湯沢のRM再評価は、価格グラフの回復線と住まいの実態のズレを直視することから始まります。定住者1,770人・高齢化率47%という数字は、いま必要なのが「販売促進」ではなく「居住の持続可能性」を底上げする地道な取り組みであることを教えています。
管理組合は回収・計画・支援の三位一体で足腰を固め、自治体は交通と情報と福祉の回路を太くする。価格の上げ下げよりも、暮らせる土台を整えた棟が長期で選ばれる—それが2020年代後半のRMの勝ち筋といえるでしょう。






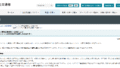

コメント