マンションにおいて「専有部分の所有者が誰であるか分からない」「所在が分からない」といった状況は、近年、少子高齢化・単身世帯増加・遠隔地転居・相続未整理といった背景を持って顕在化しています。こうした「所在不明区分所有者」の専有部分が放置されると、内装の劣化・ゴミ屋敷化・漏水・管理費滞納・廊下や外部に及ぶ悪影響など、マンション全体の管理・維持に深刻な支障をきたす恐れがあります。
そこで、令和8年4月施行によって、区分所有法に「専有部分が所在不明又は所有者が確認できない」事態を対象に、専門の管理人を裁判所が選任・命令できる制度=「所有者不明専有部分管理命令」が新設されました。
今回は、この制度(コラムでは「本制度」と呼びます)を、条文・国土交通省コメントを丁寧に読み込み、管理組合として「何をすべきか」をマンション管理士が整理していきます。
※2025年11月30日:申立先裁判所は家庭裁判所×→地方裁判所〇でしたので修正いたします。
条文解説
まずは、標準管理規約における本制度の定め(第67条の4)を読み、その趣旨・ポイントを解説します。
第67条の4の構成とポイント
条文は7項から成り立っています。主な構成を整理すると以下の通りです。
(所有者不明専有部分管理命令)
第67条の4 理事長は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分(専有部分が数人の共有に属する場合にあっては、共有を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分の共有持分)について、理事会の決議を経て、裁判所に対し、区分所有法第46条の2に基づく所有者不明専有部分管理命令を求める請求をすることができる。
2 理事長は、専有部分を管理する所有者不明専有部分管理人がその任務に違反して所有者不明専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由がある場合には、理事会の決議を経て、裁判所に対し、所有者不明専有部分管理人の解任を求める請求をすることができる。
3 所有者不明専有部分管理人は、自らの氏名又は名称、住所又は居所及び裁判所の命令を受けてその対象である所有者不明専有部分を管理する旨を遅滞なく理事長に届け出なければならない。
4 理事長は、第1項の請求に基づき選任された所有者不明専有部分管理人による所有者不明専有部分の管理に必要な経費として管理組合が負担した費用について、当該専有部分の区分所有者に請求することができる。
5 第1項の裁判所への請求を行うこととなる場合において、理事長は、前項の経費のほか、当該請求に要した費用について、弁護士費用等を加算して、当該専有部分の区分所有者に請求することができる。
6 前2項に定める費用の請求については、第60条第4項の規定を準用する。
7 第4項及び第5項に基づき請求した所有者不明専有部分の管理に必要な経費、弁護士費用等及び裁判所への請求に要した費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
この構成を通じて、次のようなポイントが浮かび上がります。
- 所有者を確認できない専有部分に対して、管理組合(理事長)が理事会決議を得て裁判所に「管理命令の請求」ができる制度。
- 管理人の選任・解任の制度的枠組みを明らかにしている。
- 費用負担・請求のルールを定め、管理組合が実務的な過重を回避する仕組みを設けている。
- さらに、請求された費用を「費用(管理組合が使用できる資金種別)」へ充当可能と定めることで、会計処理・管理上の位置付けを整理しています。
なぜ必要か:制度創設の背景
この制度が創設された背景には、従来、専有部分の所有者が不明・所在不明という状況では、たとえば管理費滞納・専有部分内の劣化放置・ゴミ・漏水等のリスクがありながら、管理組合として適切な介入手段を持たなかったという実務課題があります。
旧来は、民法上の「所有者不明建物管理人制度」などを利用せざるを得ず、マンションのような区分所有建物では適用が難しかったとも言われています。
そのため、マンション専有部分を対象とした制度整備が急務とされ、本制度が令和8年4月施行の区分所有法改正の一環で導入されました。
以下、各条項について解説します。
理事長による管理命令の請求権(第1項)
所在不明または所有者不明の専有部分について、理事長は理事会決議を経て、地方裁判所に「所有者不明専有部分管理命令」を申立てることができます。
これは令和8年4月施行の区分所有法改正(第46条の2(所有者不明専有部分管理命令))に基づくもので、放置された専有部分を管理可能にする制度です。管理組合が自力で介入できない場合に、裁判所を通じて法的に管理人を選任できる仕組みです。
所有者不明専有部分管理人の解任請求(第2項)
選任された所有者不明専有部分管理人が、任務に違反したり、著しい損害を与えるなど重大な問題を起こした場合、理事長は理事会決議を経て、地方裁判所に解任を求めることができます。
これにより、所有者不明専有部分管理人が不適切な運営を行った場合でも、管理組合が是正措置を講じられる安全弁が確保されています。
所有者不明専有部分管理人の届出義務(第3項)
所有者不明専有部分管理人は、選任命令を受けた後、速やかに理事長へ「氏名(名称)」「住所(居所)」「命令の内容」を届け出る義務があります。
これにより、管理組合が対象専有部分や所有者不明専有部分管理人の活動状況を把握でき、透明性と連絡体制が確保されます。届出は“遅滞なく”行うことが求められ、所有者不明専有部分管理人の責任を明確にする趣旨です。
管理経費の請求権(第4項)
理事長は、裁判所命令に基づく管理人による専有部分の管理に必要な経費を、当該専有部分の区分所有者に請求できます。
たとえば、管理人の活動費・修繕や点検に要した費用・予納金などが該当します。管理組合が一時的に立て替える構造ですが、最終的には所有者負担とする原則を明確化しています。
弁護士費用等の追加請求(第5項)
理事長は、裁判所への申立てに要した弁護士費用や実費なども、前項の経費に加算して区分所有者に請求できます。
この規定は、管理組合が法的手続を行う際の実務負担を補うもので、管理組合財政への影響を最小化する狙いがあります。実際には、弁護士・書類作成・予納金などの費用が含まれます。
これは、(管理不全専有部分管理命令)第67条の5第5項(当該第67条の4の準用として掲載)にも同様の条文があります。
ただし、こちらには「理事長の勧告及び指示等」第67条第4項にある、「違約金としての弁護士費用」とは別の概念となります。そもそも当該条項の所有者不明専有部分管理命令については、違約金という概念ではなく、裁判に対する費用が中心となるためです。
費用請求手続の準用(第6項)
第60条第4項(管理費滞納時の請求・督促等の規定)を準用し、これら費用請求についても同様の法的手続きで回収できると定めています。
これにより、所有者不明であっても、請求・督促・裁判所対応まで、既存の管理費請求スキームを活用できる実務上の一貫性が確保されます。
この条項についても、第67条の3「所在等不明区分所有者の除外」第6項ならびに、第67条の5第5項にも同様の条文があります。
収納金の会計処理(第7項)
第4項・第5項に基づき回収した費用や弁護士費用等の収納金は、標準管理規約第27条に定める「管理費に充当する費用」に組み入れると明示されています。
これにより、特別会計を設けずとも管理費勘定で処理でき、会計処理が明確化。管理組合の財務運営における整合性と透明性を担保します。
こちらは、第67条の3「所在等不明区分所有者の除外」第7項で詳しく解説していますので、ご案内します。
国交省の補足コメントに対する解説
国土交通省が改正標準管理規約の解説資料等で示している3つの補足的コメント(50ページ、資料87枚目)が、管理組合実務においてポイントとなります。こちらでは、いくつかの切り口に分けて解説します。
制度のマンション専用化と手続きの整備
国交省コメント①では、「第67条の4及び第67条の5関係」は、令和7年の区分所有法改正で創設された“マンションに特化”した財産管理制度であることを明示しています。コメント文では「この標準管理規約においては、同一の敷地・建物を共有する利害関係人として、管理組合が両制度を活用するに当たっての手続規定を設けている」旨が記されています。
この点を深掘りすると、ポイントは「マンション」という区分所有建物特有の構造・共用部分・専有部分・敷地・附属施設が混在する環境に対し、専有部分の所在不明という事態が、共用部分・敷地・附属施設全体に影響を及ぼす可能性があるため、専用の管理制度が必要とされたということです。
実務上、管理組合はこの手続きの存在を知っておくことで、所在不明専有部分という従来“抜け穴”だったリスク領域に対応可能になりました。たとえば、長期未使用・滞納・室内放置ゴミなど「放置危険案件」に対して、理事長・理事会が主体的に対応を主導できるようになった点は大きな変化です。
詳しくは、令和7年マンション標準管理規約改正について(令和7年10月26日 国土交通省マンション管理適正化シンポジウム資料28枚目、27ページ)に分かりやすい説明があります。
ただし、手続きには理事会決議・裁判所請求・管理人選任などが含まれるため、次章で詳しく解説しますが、管理組合としてあらかじめ「手続きフロー」「想定費用」「内部規程(理事会承認・予備調査)」を整備しておくことが望まれます。
所有者不明管理人と管理不全管理人の区別
コメント②では、「区分所有法上、所有者不明専有部分管理人(当条項)と管理不全専有部分管理人(第67条の5)はその性質の違いから実施できる業務に差が設けられており、この標準管理規約においても、区分所有法上の差異に合わせて書き分けているので、注意が必要である」とされています。
具体的には、
✅所有者不明専有部分管理人は、「総会の招集通知を受領し、区分所有者に代わって総会において議決権を行使することができる」
✅管理不全専有部分管理人にはその議決権行使の権能は与えられていない
とされています。
この違いは、管理実務において重要です。たとえば、所在不明専有部分の議決権・出席義務をどう扱うかという場面で、制度の種類に応じた対応が求められます。
所在不明という「所有者そのもの」が把握できない段階だからこそ、議決権を管理人が行使できる仕組みを設けることで、集会意思決定の停滞を防ぐ意図があります。
対して、管理不全はあくまで「所有者がいるが管理がなされていない」ケースなので、議決権の行使を管理人に委ねる趣旨にはなっていない、という整理です。
国土交通省の補足コメントが、第67条の4と第67条の5についてまとめて紹介されていたため、紹介しましたが、管理不全専有部分管理人については、第67条の5であることから、改めてそちらでも紹介します。
そして、管理組合としては、専有部分の状況把握を行い「どの制度が適用可能か」を区別できるようにしておく必要があります。
また、国土交通省コメント②に関連する所として、標準管理規約第43条、46条、47条も確認する必要があります。
※順次改正後の規約対応に更新予定



費用負担の明確化と実務リスクへの備え
コメント③では、「第67条の4第4項及び第67条の5第4項の「管理組合が負担した費用」とは、主に管理人が当該専有部分を管理するために必要となる経費について、裁判所への請求時に納入が求められる予納金を想定しているものである」と明記されています。
この点から、実務上以下が留意点です。
✅裁判所請求にあたっては、予納金(管理人選任・命令申立て等)という形で費用が発生する可能性がある。
✅管理組合がまず負担するが、条文上、当該専有部分の区分所有者に請求できるとされている。つまり、理事長・理事会としては「まず管理組合で立替えておく」「その後請求可能である旨を規約・理事会決議で明示しておく」ことが実務上安心です。
✅会計処理上、「請求した費用は第27条(管理費)に定める費用に充当できる」とされていることから、回収した金額は管理費会計の収入として処理し、通常の管理費支出の補填に充てることができる。
以上より、管理組合としては「所在不明専有部分」という潜在リスクが発生したときに、手続き・負担の想定・議会(理事会・総会)説明をあらかじめ準備しておくことが賢明です。
管理組合として対応すべき事項
一部、前章でも紹介しましたが、実務上、管理組合(理事会・理事長)として本制度を活用・準備するために、下記のような対応事項を整理します。
実務上の留意点
まず、実務上の留意点として、改めて以下を整理します。
✅「区分所有者を知ることができない」または「その所在を知ることができない」という文言が要件。ここでは「登記簿上の名義人」であっても実際に所在が不明であれば該当し得ること、理事会として実態調査・所在確認に向けた記録を残す必要があります。
✅裁判所に請求をする際は、理事会の決議を経る必要があります(第67条の3、67条の5のそれぞれ第1項も同様の記載)。管理組合のガバナンスとして、理事会・総会の承認を踏まえて進めるべきです。
✅費用請求の際に、負担対象となるのは「管理組合が負担した費用」および「裁判所請求に要した費用等(例えば弁護士費用)」であること。理事長はこれを明確に、当該専有部分の区分所有者に請求できます。
✅請求できる費用は、「第27条に定める費用」に充当できるとされており、会計処理を明確にすることで滞納・不履行による会計リスクへの備えもできます。
所在不明専有部分の早期発見・調査体制の整備
第一段階として、所在不明の可能性がある専有部分を早期に把握できる体制を整えることが重要です。具体的には以下を検討すべきです。
✅区分所有者の転出入・相続・長期空室・管理費滞納のデータを定期的にチェック。
✅長期間管理費・修繕積立金の滞納がある専有部分、室内・玄関前に荷物・ゴミが溜まっている報告がある専有部分、居住実態が確認できない専有部分などを「所在不明等の前兆」として早期警戒対象とする。
✅管理規約・使用細則等に「転出届・居住実態届出」「所在確認義務」「所在不明と認定しうる条件」を明記。
✅所在不明の疑いがある場合は、管理会社・理事会が転入転出の状況・住民票・登記簿(所有者変更登記)等を定期的に確認できる仕組みを確立。
こうした体制整備により、「所有者が誰か分からない」「所在が分からない」という状態が発生してから慌てて対応するのではなく、予備段階でリスクを可視化・管理できるようになります。
これは、まさに「長期的な視点でマンション管理体制を構築する」という点で重要な取組です。
理事会・総会の手続き・規約整備
所在不明専有部分への対応を制度として組み込むには、理事会・総会・管理規約という管理組合のガバナンス構造を整備しておく必要があります。具体的には以下が挙げられます。
✅今回紹介する条文に改めることを前提として、管理規約・使用細則等に「所在不明専有部分管理命令請求」の制度趣旨・手続き・費用請求の条項を盛り込んでおく。
✅規約改正に合わせて請求に至った場合の理事長の役割を明確にしておく。条文通りの流れを別紙手続き図にして理事会・理事向けに共有しておくとより実務的。
✅総会報告・理事会共有用として「所在不明専有部分の現状」「対応可能な制度」「想定費用・リスク」を明確にして、区分所有者への説明責任(アカウンタビリティ)を果たす。これにより、請求に至った場合でも、管理組合の透明性・公平性が担保される。
決議要件・招集通知要件・議決権取扱い(所在不明区分所有者の議決母数からの除外等)など、改正区分所有法の関連制度とも整合を取っておくことが大切です。
裁判所請求・管理人選任・費用請求の実務フロー
所在不明専有部分管理命令を実際に請求・運用するにあたって、管理組合として以下の実務フローを確認しておくことが望まれます。手続きにあたっては、マンション管理士ではなく、弁護士に相談する必要があります。
✅所在不明専有部分対象の選定:理事会で「所在を確認できない専有部分」の候補を挙げ、調査・記録を残す。
✅理事会決議:対象・請求理由・見込費用・リスクなどを理事会で決議。議事録保存。
✅裁判所申立て:利害関係人(管理組合・理事長・他の区分所有者等)から、裁判所へ請求。裁判所にて、管理人選任・命令発令。
✅管理人の届け出:選任された管理人は、氏名・住所・居所・命令を受けて管理する旨を理事長に遅滞なく届け出る(条文第3項)。
✅管理実務開始:専有部分・関連共用部分・敷地・附属施設・動産等に対して管理人が管理・処分を行える。(区分所有法第46条の3参照)
✅費用の精算・請求:管理組合が先行して支払った費用を、当該専有部分の区分所有者に請求する(条文第4項・第5項)。この際、弁護士費用・裁判所申立て費用も含めて請求可能。会計処理上は「費用」として第27条の規定により管理費に充当が可能。
✅会計・収納対応:未払が発生した場合、管理組合として収納・滞納処理の体制をあらかじめ整えておく。また、請求しても支払いされないケースも想定し、管理規約・使用細則には滞納時の対応(議決権停止・修繕積立金差し押さえ等)も定めておきましょう。
以上が大枠の流れですが、令和8年4月以降は具体的な事例も出てくると思います。現在は事例が無いので、対応イメージとして紹介している点があります事をご了承ください。
未然防止と長期管理の観点からの対策が非常に重要
本制度はあくまで「疑義のある専有部分を顕在化させて管理・処分を可能にする」後発的な制度です。
理事会としては、そもそも「所有者不明」という状態をつくらない、あるいは早期に発見・対応するための体制構築が重要です。以下の対策が有効です。
✅日常点検・巡回報告制度を設ける:管理会社・管理組合ともに、専有部分前面・廊下・パイプシャフト・排水管などの状況を定期に確認し、「異常あり」の報告を蓄積。
✅長期空室・無人転居・相続未整理のケースを識別:所有者変更登記の未了・住民票の転出超過・荷物滞留の報告などを指標に、所在確認が難しい専有部分を早期に特定。
✅滞納・クレーム・ゴミ放置などの併発状況に注視:所在不明専有部分は、管理組合運営コストも増大し、隣接住戸・共用部分への影響が顕在化しやすいため、異常サインを早期に把握し、理事会で議論できる体制を整えておく必要があります。
✅管理費・修繕積立金の滞納防止策:所在不明案件が発生すると、管理費滞納による管理組合収入の毀損・滞納リスク増大を招きます。滞納初期段階から理事会・管理会社でフォロー体制を敷き、「所在不明リスク」と「滞納リスク」が交錯しないようにしておく。
所有者不明専有部分管理命令に備え、管理組合が今からできること
「所有者不明専有部分管理命令」は、所在不明区分所有者への対応を法的に可能とする新制度です。放置された専有部分が管理不全や安全性の低下を招く前に、理事会が主導して対応できる点で極めて実務的な意義があります。
管理組合としては、
①所在不明専有部分の早期発見と記録体制
②理事会決議・規約整備などガバナンスの明確化
③裁判所申立てや費用精算を見据えた会計処理の準備
――この三点を今のうちに整えておくことが重要です。
制度は便利な一方で、申立てや費用回収には時間もコストもかかります。したがって、まずは「制度を知る」だけでなく、「実際に動ける体制を整える」ことが、長期的なマンション管理への第一歩となります。



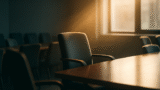


コメント