東京都心で中小規模のオフィスビルが急速に姿を消し、マンションへ転用されるケースが増えています。ザイマックス総研の調査によれば、延べ床面積990〜1万6500平方メートルのビルの数は2025年末までに約8700棟となり、10年前より400棟以上減少する見通しで、床面積に換算すると東京ドーム25個分ものオフィスが失われる計算です。オーナーの高齢化や老朽化に伴う修繕費の増大を背景に、ディベロッパーが買い取って需要の高いマンションに建て替える例が目立ち始めました。
オフィスビルはなぜマンションに変わるのか
大きな理由は二つあります。第一に 中小ビルの競争力低下 です。東京都心では森ビルなどによる大規模な再開発が進み、供給されるオフィスの多くは延べ床面積10万平方メートル以上の高層ビルに集中しています。
築年数が30年以上を超えると設備が陳腐化し、新しいビルに比べると見た目や設備も劣るため、優良テナントが退去して稼働率が低下しがちです。日経の記事が紹介した五反田ファーストビルは大口テナントの退去によって稼働率がほぼゼロになり、東京建物がタワーマンションに建て替える方針を決めました。
第二に マンション用地の不足と需要の高さ です。新築マンションの供給戸数は2025年1〜6月までに前年同期比11%減と4年連続で減少していますが、東京23区の平均販売価格は1億円を超えて過去最高水準にあり、住宅の需要がオフィス需要を上回っていることがデータからも伺えます。そのため、高価格帯でも事業が成立しやすく、デベロッパー各社は用地取得に熱を入れています。
都心マンションの購入を支える「パワーカップル」
需要側の主役は、高学歴・高所得の共働き世帯、いわゆるパワーカップルです。共働きで世帯年収が高い層が都心の分譲マンションを購入する流れは根強く、記事でも供給減にもかかわらず購入層の価格耐性が高いことが指摘されています。
彼らが都心マンションにこだわる理由には「職住近接による通勤負担の軽減」「子育て環境の充実」「都心の文化・医療へのアクセス」などが挙げられます。例えばJR目白駅から徒歩3分の好立地に建つ「イノバス目白」は1億4000万〜2億円という高値にもかかわらず完売が見込まれています。
こうした物件は高所得層にとって資産形成の手段にもなっており、他の資産と比較して値下がりが小さいという期待もあります。
ところが、最近はパワーカップルでも購入をためらうケースが増えています。新築価格の高騰に加え金利の上昇が進み、30〜40代前半の世帯が1億円超の住宅ローンを組むのは容易ではありません。
また、マンション価格は上がり続けている一方で給与の伸びが追いつかないため「欲しい物件がない」「予算に見合う広さが確保できない」と感じる層も増え、賃貸や郊外への移住を検討する事例もあります。
地方を置き去りにする都心の住宅偏重
都市部では人口流入が続いています。総務省の統計によると、東京都23区の転入超過数は2022〜24年の3年間で約13万4000人に達し、コロナ禍前の水準に戻りつつあります。
マンションなど集合住宅の延べ床面積比率も2021年に38.9%と10年前より上昇しており、都心への住宅供給が増えれば人口集中に拍車がかかるでしょう。
一方で、地方では人口減少と高齢化が進み、空き家の増加や商店街の衰退など地方の空洞化問題が顕在化しています。都市への転出により地方の労働力が減少し、税収も減ることで行政サービスの維持が難しくなるという悪循環が起きています。マンション転用が進む都心と比べ、地方では住宅需要が伸び悩み、古い住宅や空き地の有効活用が進まない状況です。
地方から若者が流出し続ければ、東京圏のインフラや教育機関が過密化し、地方の産業が衰退して全国経済のバランスが崩れる恐れがあります。国土交通省が掲げる「コンパクトシティ」政策や地方創生の取り組みは、こうした課題への対策として重要ですが、実効性はまだ不十分です。
今後は地方にも魅力的な雇用や住環境を整備し、国内移住やテレワークを促進することが求められるでしょう。
開発ラッシュに伴う社会的課題
タワーマンションの林立は都市景観や教育環境にも影響を与えています。日経の記事では、有名進学校である桜蔭や女子学院が隣接地のタワーマンション計画に反対した事例が紹介されています。
単に経済合理性だけではなく、地域全体の将来像や公共性を考慮する街づくりが必要だと指摘されています。
大規模マンションは周辺環境への日照や風環境の影響、保育園・学校の受け入れ能力、交通混雑など様々な課題を抱えます。都心では歩行者空間や緑地の確保が難しくなりがちで、住民同士のコミュニティ形成にも影響が出る場合があります。
また、建設コストの高騰や資材高によってデベロッパーのリスクが増し、売れ残りリスクが顕在化すれば市場全体のバブル崩壊につながる懸念もあります。
以下の記事に、『桜蔭学園、隣地タワマン建設で都を提訴した3つの理由』を紹介しています。
マンション市場の行方と投資の視点
今後のマンション市場はどのように推移するのでしょうか。日本銀行は長く続いた超低金利政策を2024年に転換しつつあり、住宅ローン金利は緩やかに上昇しています。
金利の上昇は購入希望者の借入可能額を減らすため価格の調整要因となりますが、インフレや建設コストの上昇はマンションの原価を押し上げるため、値下がりは限定的と見る専門家も多いです。特に都心の優良エリアは供給が限られており、希少性が価格を支える構造が続くでしょう。
投資家の視点では、円安や外国人投資の増加が価格の押し上げ要因になっています。海外投資家にとって東京の物件は相対的に割安と映ることが多く、賃料の安定性も魅力です。
一方で内需だけでは消化しきれないほどの高価格帯物件が増えると、景気悪化や金融引き締めのタイミングで急激な価格調整が起こるリスクも否めません。購入を検討する際には、物件の立地や管理状態だけでなく、将来の金利動向や人口動態を踏まえた長期の視野が欠かせません。
子育て世代と住宅選択の多様化
現在のマンション市場がパワーカップル向けの高価格物件に偏ることで、一般的な子育て世帯や単身者が都心に住めない状況が広がっています。政府の住宅ローン減税や補助金制度はあるものの、1億円前後の住居を購入する際の負担は大きく、教育費や老後資金とのバランスを考えると躊躇する層が多いのが現実です。
そのため、リノベーション済みの中古マンションや郊外の戸建て住宅、賃貸に住みながら資産運用を行うといった住宅選択の多様化が進んでいます。
中古市場では築古物件を現代的な内装に改修して販売するビジネスが拡大し、デザイン性や機能性に優れたリノベ物件が若いファミリー層に支持されています。郊外では新線開通やリモートワーク普及により、都心から30〜40分圏内の街への注目が高まっています。
未来の東京と持続可能な街づくり
さらに、マンション転用の流れが東京の未来にどのような影響を与えるかを考えます。都市機能がコンパクトにまとまることで公共交通網の効率化や行政サービスの集中が可能になる一方、極端な高密度化は災害時のリスクや環境負荷を増大させます。
2050年頃には都心部の人口がピークに達し、さらなる高層化が進むと予測されていますが、気候変動への対応や防災対策、歴史的景観の保全といった長期的な視点が欠かせません。
また、地域コミュニティの維持や多様な世代が共生できる街づくりも重要な課題です。子育て世帯から高齢者、外国人労働者まで多様なバックグラウンドの人々が安心して住める環境を整えるためには、住宅の供給だけでなく保育施設や医療・介護施設、公園といった共用空間の充実が求められます。
建築物の高性能化に加え、エネルギー自給自足型のスマートシティ構想や自然災害に強い都市インフラの整備が、未来の東京の価値を左右するでしょう。
おわりに—バランスある都市政策を
中小オフィスビルの減少とマンション転用が進む背景には、東京という都市の持つ圧倒的な魅力とパワーカップルの旺盛な需要がある一方、高騰する価格や地方の空洞化、環境・教育への影響といった課題も潜んでいます。
今後も都心への投資は続くでしょうが、街の将来像や公共性に配慮した開発を進めることが重要です。
政策面では、都市と地方の均衡ある発展を目指す施策が一層必要です。
地方の魅力的な雇用創出、都市に依存しない生活インフラの整備、オンライン教育やリモートワークの普及により、人口の流動性を高めることが求められます。マンション価格の高騰が続く中、住宅政策や税制も見直し、一般の実需層が無理なく住まいを選べる環境を整えることが社会全体の安定につながるでしょう。
東京ドーム25個分のオフィスがマンションになるという事実は、日本の都市政策や住宅事情の転換点を象徴しています。
この流れを単なる不動産ビジネスとして眺めるのではなく、都市と地方、住宅とオフィスのバランス、持続可能な社会のあり方という観点から見つめ直すことが必要です。
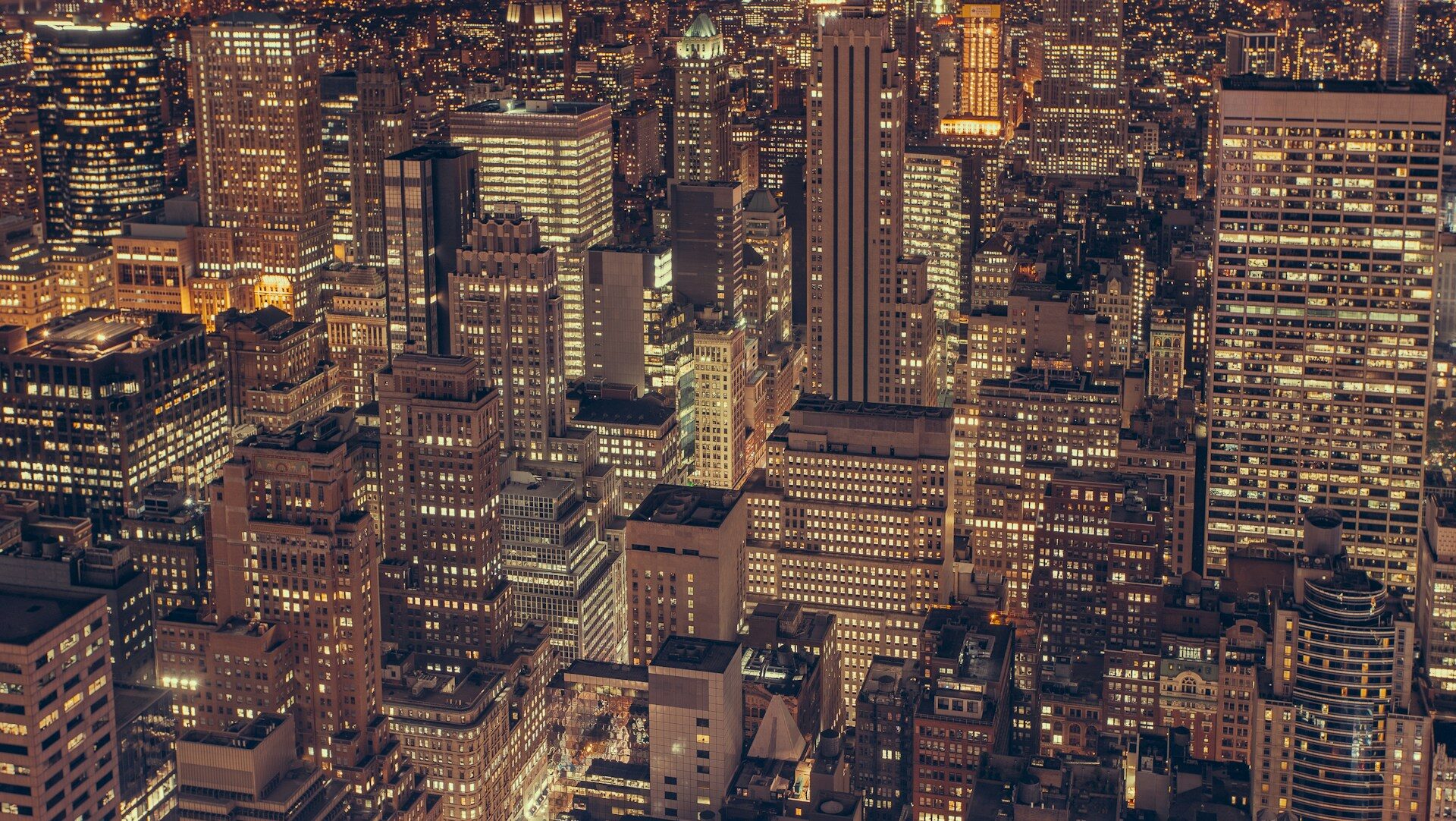








コメント