令和8年4月の区分所有法改正により、マンション管理の実務に大きな転換点が訪れます。それが「管理不全専有部分管理命令」の創設です。
専有部分内部の問題は、これまで管理組合の介入が難しい領域でした。しかし実際の現場では、室内の設備不良を放置した結果の漏水被害、ゴミ屋敷化による害虫発生、長期不在による悪臭や滞納など、専有部分が原因で建物全体に深刻な影響が及ぶケースが後を絶ちません。
本稿では、標準管理規約第67条の5の条文と国交省コメントを踏まえ、制度の趣旨と実務対応をマンション管理士の視点から詳しく解説します。
条文解説
まず初めに、標準管理規約における本制度の定め(第67条の5)を読み、その趣旨・ポイントを解説します。
第67条の5の構成
条文は以下の5項から成り立っています。
(管理不全専有部分管理命令)
第67条の5 理事長は、区分所有者による管理が適切に行われていない専有部分について、理事会の決議を経て、裁判所に対し、区分所有法第46条の8に基づく管理不全専有部分管理命令を求める請求をすることができる。
2 理事長は、対象物件内の専有部分を管理する管理不全専有部分管理人が管理不全専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由がある場合には、理事会の決議を経て、裁判所に対し、管理不全専有部分管理人の解任を求める請求をすることができる。
3 管理不全専有部分管理人は、自らの氏名又は名称、住所又は居所及び裁判所の命令を受けてその対象である管理不全専有部分を管理する旨を遅滞なく理事長に届け出なければならない。
4 理事長は、第1項の請求に基づき選任された管理不全専有部分管理人による管理不全専有部分の管理に必要な経費として管理組合が負担した費用について、当該専有部分の区分所有者に請求することができる。
5 前条第4項から第7項の規定は、前項の費用の請求について準用する。この場合において、「所有者不明専有部分管理人」とあるのは「管理不全専有部分管理人」と、「所有者不明専有部分」とあるのは「管理不全専有部分」と読み替えるものとする。
以下、具体的に各項について、解説していきます。
管理不全専有部分の定義と典型例
そもそも管理不全専有部分とは、どのようなものを指すのでしょうか。
管理不全専有部分とは、区分所有者が本来行うべき専有部分の管理行為を怠り、建物全体や他住戸に具体的な不利益を与えている状態を指します。
典型例は次のようなものです。
✅室内設備の故障を放置して階下へ継続的に漏水させている
✅ゴミの堆積により害虫が発生し、共用部分へ広がっている
✅玄関前に物品が溢れ、避難経路の安全を阻害している
✅悪臭や液体漏出など衛生上の問題が発生している
これらは単なる“部屋の散らかり”ではなく、建物全体の管理に影響する具体的事実である点が重要です。
理事長が裁判所に申立てる仕組み(第1項)
条文第1項は、理事長が理事会決議を経て、裁判所に管理不全専有部分管理命令を求める申立てを行うことを明記しています。従来、管理組合には専有部分内部の改善を強制できる明確な手段がありませんでしたが、この制度によって法的なアプローチが可能となります。
申立ての代表的な流れは、以下のように整理できます。
✅管理不全の状況把握(管理員報告・苦情・写真)
✅区分所有者への改善要求(段階的な文書通知)
✅理事会による申立て決議
✅理事長による裁判所への正式申立て
✅裁判所による調査・判断
✅管理不全専有部分管理人の選任
管理組合そのものが専有部分へ立ち入るのではなく、裁判所が選任する「管理人」が改善の実務を担う点が制度の核心です。
管理不全専有部分管理人の解任請求(第2項)
第2項では、管理不全専有部分管理人が不適切な行為を行った場合に、理事長が裁判所へ解任を求められることを規定しています。
管理不全専有部分管理人は、専有部分内部に直接立ち入って改善行為を行う強い権限を持ちます。ゆえに、その権限の行使が不適切であった場合に備え、制度は「安全弁」を設けています。
解任の対象となる行為の例としては:
✅当該管理人自身が専有部分や共用部分に著しい損害を与えた場合
✅管理不全の改善に必要な行為を怠る場合
✅専有部分で不適切な措置を行い、他の区分所有者の利益を侵害する場合
制度として、管理不全専有部分管理人が「万能化」することを防ぎ、管理組合の利益を守る役割を担う規定と言えます。
管理不全専有部分管理人の届出義務(第3項)
第3項は、管理人が選任された後の報告義務に関する規定です。管理不全専有部分管理人は、
✅氏名または名称
✅住所または居所
✅「裁判所の命令を受けて管理不全専有部分を管理する」旨
を、遅滞なく理事長へ届け出る必要があります。
届出が義務付けられている理由は、管理組合が管理不全専有部分管理人の活動状況を把握し、必要に応じて協力・連携できるようにするためです。特に、管理人が専有部分へ出入りする場合には、共用部分の鍵管理・立ち入り動線など、管理組合との調整が不可欠となります。
この規定は、管理人の“透明性”を確保し、管理組合との円滑な連携を前提として位置づけられています。
管理組合が負担した経費の区分所有者への請求(第4項)
第4項は、管理組合が管理不全専有部分の改善のために立替えた費用を、その専有部分の区分所有者に請求できることを認める規定です。管理不全専有部分管理命令に係る費用の多くは、
✅裁判所へ納入する予納金
✅管理人の報酬
✅管理人が行う調査・清掃・修繕等の費用
などであり、通常は管理組合が一時的に支払います。
管理組合が法的手続を利用する際、費用の負担を自ら背負ってしまうと制度が使えなくなります。そのため、法は明確に「最終的には区分所有者に請求できる」という仕組みを整えています。
これは管理組合が制度を活用するうえで非常に重要な“財務上の後ろ盾”であり、制度運用の実効性を担保する規定です。
所有者不明専有部分に関する規定の準用(費用請求の実効性確保)(第5項)
第5項は、管理不全専有部分に関して管理組合が立替えた費用を区分所有者へ請求する際、前条67条の4の第4項〜第7項をそのまま準用するという重要な規定です。これにより、管理組合は単なる改善費だけでなく、申立てに要した弁護士費用等も含めて区分所有者へ請求することが可能になります。
準用される内容には、
✅立替えた経費の請求
✅弁護士費用等の加算
✅管理費滞納と同様の督促手続の利用
✅回収した費用の管理費等への充当
といった請求・回収のルールが含まれています。
管理不全住戸は滞納や連絡不能と結びつきやすく、通常の請求手続では実効性が乏しくなることがあります。第5項により、管理組合はより強い回収の手段を使えるようになり、結果として 「立替え損」のリスクを減らし、制度の実効性を確保することにつながります。
国交省コメントに対する解説
国交省コメントは、所有者不明制度と管理不全制度の違いや、各制度の目的と権限範囲を整理した公式補足です。条文だけでは分かりにくい運用上の注意点を理解するうえで必要なため、具体的に紹介します。
所有者不明制度との違いを正しく理解する
国交省コメントは、「所有者不明専有部分管理命令」と「管理不全専有部分管理命令」が制度上明確に別物である点を強調しています。第67条の4「所有者不明専有部分管理命令」でも紹介しましたが、特に次の2点が重要です。
✅所有者不明制度は“議決権の代行”が可能だが、管理不全制度にはその権限がない
✅管理不全制度は“専有部分の安全性・衛生改善”に限定した制度である
つまり、管理不全専有部分管理人は、所有者の代わりとしてマンションの意思決定に参加する存在ではなく、あくまで技術的・管理的な介入者という位置づけです。
予納金の性質と財務への影響
コメント③が指摘するように、申立て費用の中心は予納金です。管理組合がまず負担する必要があり、後日区分所有者へ求償する仕組みのため、実務としては「立替えられる財源」を平時から確保しておく必要があります。
特に中小規模の管理組合では、財務計画への組込みが不可欠になります。
その他、国土交通省に関する補足コメントについては、前条の第67条の4「所有者不明専有部分管理命令」でも紹介していますので、そちらをご参照ください。
管理組合として対応すべき事項
管理不全専有部分管理命令を実務で活用するには、制度の理解だけでなく、事前の準備体制が不可欠です。ここでは管理組合が具体的に備えるべき事項を整理します。
管理不全の“客観的証拠”を蓄積する仕組み
管理不全専有部分管理命令の申立てでは、管理組合の主観的判断ではなく、裁判所に対して「客観的事実」を提示できるかどうかが極めて重要になります。したがって、日常管理の段階から、問題の兆候を系統的に記録し、後から第三者が見ても状況が明確に分かる形で証拠化しておく必要があります。
証拠として有効とされるものには、苦情の受付記録、管理員による日誌、共用部分に現れた影響の写真、漏水時刻のメモ、臭気の発生状況、害虫確認の記録などが含まれます。これらは単発で存在しても弱く、時間軸で整理されていることが重要です。裁判所は「発生時期」「継続性」「影響範囲」の3点を重視するため、日時入りの記録を積み重ねることで、管理不全の深刻性が裏付けられます。
また、日頃から管理員・理事会・管理会社の間で、異常兆候を速やかに共有できる仕組みを整えておくことも、証拠の蓄積と質の向上に直結します。
理事会決議の内容と議事録整備
管理不全専有部分管理命令の申立てには理事会決議が必須とされていますが、ここで求められるのは単なる形式的な承認ではありません。裁判所は「理事会がどのような事実関係を把握し、どのような判断プロセスを経て申立てに至ったのか」を重視します。そのため、議事録には問題の経緯をできる限り正確かつ客観的に記す必要があります。
具体的には、管理不全と判断した根拠(漏水の継続・衛生被害・苦情の件数など)、管理組合として実施してきた改善要請の履歴、当該区分所有者との連絡状況、管理員からの報告内容、他住戸への影響の程度、申立てに至るまでの判断過程と理由を明確に整理することが求められます。また、管理会社の見解や技術的意見を理事会で共有した場合は、それも議事録に含めておくと、裁判所の判断を支える材料となります。
議事録は後から裁判所に提出される可能性が高いため、曖昧な表現を避け、事実と評価を分けて記載するなど、証拠性を意識した作成が重要になります。
適切な改善要請の実施
管理不全の問題は、内容証明郵便を送ったからといって改善されるものではありません。むしろ、管理不全住戸の多くは「長期不在」「高齢化」「孤立」「精神的問題」「コミュニケーション断絶」を背景としており、反応が返ってこないケースが一般的です。そのため、管理組合としては「形式的な手続」ではなく、「実際に試みる価値のある働きかけ」を段階的に実施し、合理的な努力を尽くしたことを示す必要があります。
具体的には、まず管理会社や管理員が日常接触の中で声掛けを行い、貼紙やポスト通知を行う方法があります。そのうえで、郵送による通知を複数回試み、一定期間返答がない場合には、理事長名での正式な文書による改善要請へと進みます。これらの過程で、郵便物が受け取られているか否か(不在票・持ち戻りなど)も記録すると、裁判所への説明が容易になります。
最終段階として内容証明郵便を送付することで、管理組合ができる限りの努力を尽くしたことを客観的に示すことが可能になります。ポイントは、「相手が応じないだろう」と思っても段階的に行うことで、裁判所に対し申立ての正当性を裏付けられる点にあります。
管理会社との連携強化
管理会社は、日常管理の最前線にいる立場として、管理不全の兆候を最も早く察知できる存在です。そのため、管理会社との連携体制を強化し、情報共有の質とスピードを高めることが、管理不全への早期対応に直結します。
具体的には、管理員報告書に「臭気」「害虫」「水漏れ痕」「異常なゴミ排出」「郵便物の滞留」「生活音の長期不在」といった管理不全につながるチェック項目を追加し、異常が確認された際には写真付きで報告するルールを設けることが効果的です。また、管理会社側で気付いた異常を定例報告ではなく、随時報告として理事長へ即時連絡する体制を構築することも重要です。
さらに、管理会社は同種事例の経験を多く持っているため、改善要請の文案、対応履歴の残し方、理事会における判断材料の提供など、専門的な支援も期待できます。管理不全住戸への対応は長期化する傾向があるため、管理会社と理事会が一体となって対応し、情報が埋もれないよう記録を一元化することが効果的です。
管理不全を放置しない“強い管理組合”へ
管理不全専有部分管理命令は、専有部分内部の問題に苦慮する管理組合にとって革新的な制度です。放置住戸や継続的な漏水など、建物全体の安全や資産価値を損なう事案に対して、裁判所を通じた実効的な対応が可能になりました。
ただし、制度は準備の整った管理組合にしか使いこなせません。証拠の蓄積、理事会決議、改善要請、財源確保、管理会社との連携など、事前の仕組みづくりこそが成功の鍵となります。
専有部分の問題を“仕方ない”で終わらせない。この制度を正しく理解し、運用できる管理組合こそが、これからのマンション価値を守る重要な存在になるでしょう。


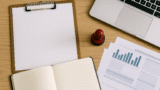




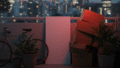
コメント