マンション市場の動向は、購入者や投資家だけの話ではありません。既存マンションに住む区分所有者や管理組合にとっても、無関係ではないテーマです。金利環境や価格動向、供給状況の変化は、既存マンションの管理組合運営や資産価値にも確実に影響します。
本記事では、2024年時点のマンション市場の動きを整理したうえで、既存マンションの管理組合運営や資産価値に、どのような影響が及ぶのかを専門家の視点で解説します。 数字の解説にとどまらず、管理・運営への影響に焦点を当てます。
一次データ(公式統計)
首都圏 新築分譲マンション市場動向(株式会社不動産経済研究所)
※2024年度首都圏新築分譲マンション供給・価格等に関する公式調査
【大幅減】首都圏新築マンション供給、過去最少を記録
不動産経済研究所が2025年4月21日に発表したデータによると、2024年度(2024年4月~2025年3月)の首都圏における新築分譲マンションの発売戸数は2万2,239戸となり、前年度比で17.0%の大幅な減少となりました。
これは、1973年度の調査開始以来、過去最少の供給戸数であり、新築供給が絞られることで、既存マンションの相対的な市場価値が高まりやすい環境にあることを示しています。過去最多であった2000年度の9万5,479戸と比較すると、市場の規模が大きく縮小していることが鮮明にわかります。
エリア別に見ると、東京23区が8,272戸(シェア37.2%)で最も多く供給されていますが、こちらも前年度比で25.5%減と大きく落ち込んでいます。その他のエリアでは、東京都下が1,993戸(同12.6%減)、神奈川県が4,585戸(同28.0%減)、千葉県が3,964戸(同3.5%減)となっており、埼玉県のみ3,425戸(同17.0%増)と供給戸数を増やしています。しかし、首都圏全体としては大幅な供給減という厳しい状況です。
【契約率の低迷】2年連続70%割れ、販売在庫は増加傾向
供給戸数が減少する一方で、需要の勢いも鈍化していることがデータから読み取れます。2024年度の初月契約率は66.8%となり、前年度の69.9%から3.1ポイント低下し、2年連続で70%を下回る結果となりました。
エリア別に見ると、東京23区が69.8%と最も高い契約率を維持しているものの、前年度からは0.1ポイントの微減となっています。東京都下は60.4%(同10.7ポイント減)、神奈川県は67.5%(同1.5ポイント減)、千葉県は67.2%(同10.0ポイント減)と軒並み契約率を落としており、埼玉県のみ61.8%(同0.9ポイント増)とわずかに上昇しています。
この契約率の低迷を背景に、2024年3月末時点の販売在庫数は6,116戸となり、前月(5,661戸)から455戸増加しています。これは、販売在庫が前月以上に翌月に繰り越されたこととなりました。
【価格高騰が止まらない】平均価格は過去最高を更新
需給バランスが緩和傾向にあるにも関わらず、首都圏の新築マンション価格は依然として高騰を続けています。2024年度の戸当たり平均価格は8,135万円、1㎡当たり単価は123.0万円となり、いずれも前年度比で平均価格が7.5%(570万円増)、㎡単価が6.9%(7.9万円増)のアップとなりました。平均価格は4年連続、㎡単価は13年連続の上昇であり、その勢いは衰えていません。
特に東京23区の価格高騰は顕著で、戸当たり平均価格は1億1,632万円(前年度比11.2%増)、㎡当たり単価は177.3万円(同10.1%増)と、2年連続で戸当たり価格が1億円を突破し、二桁の上昇率を示しています。東京都下、神奈川県、埼玉県、千葉県においても、戸当たり価格、㎡単価ともに前年度を上回っており、首都圏全体で価格水準が一段と引き上げられています。
この価格高騰の背景には、2024年問題による労務費の一段のアップや、資材費、用地費の高騰といった建設コストの上昇が大きく影響していると考えられます。建設物価調査会によると、3月の東京地区におけるマンションの建築費指数(速報値)は前年同月比5%高となっています。
中小デベロッパーの苦境と大手デベロッパーの戦略
日経の記事では、新築マンション供給戸数の減少の背景として、不動産デベロッパーにとって建設費の高騰と用地の取得難が当面続くことが指摘されています。特に中小デベロッパーは採算確保に苦しんでおり、取得する用地を厳選する傾向が強まっています。郊外においては、一般消費者の手が届く価格帯での物件供給が難しくなっており、中小デベロッパーの経営リスクが高まっています。
一方、体力のある大手デベロッパーは、価格が高くても需要が底堅い都心部を積極的に攻める戦略をとっています。大京の社長は「需要が集中する都心立地は、供給側も企業体力のある大手事業者になっている」と述べています。東京23区における大規模マンションの開発が難しくなる中、コンパクトな都市型マンションを手掛けるデベロッパーが増えているという分析もあります。
また、中小デベロッパーは、通常の分譲マンション以外に活路を見出そうとしています。例えば、地方のシニア富裕層をターゲットとしたマンション開発や、木造建築のノウハウを活かした福祉施設などの建築分野への進出といった動きが見られます。
消費者の選択肢の変化と市場の二極化
新築マンション価格の高騰により、一部の消費者は戸建て住宅へと流れる傾向も見られます。建て売り戸建てを大量供給するパワービルダーは、スケールメリットにより価格を抑えることができ、マンションと比較して割安感があるため、特に一次取得者にとって現実的な選択肢となっています。
このような状況下で、首都圏のマンション市場は都心部の高額物件と、郊外の価格を抑えた物件という二極化が進む可能性があります。都心部では、富裕層や共働き世帯を中心に、利便性の高い新築マンションへの根強い需要が見込まれる一方、郊外では価格に対する消費者の目が厳しくなり、よりコストパフォーマンスの高い物件が求められるでしょう。
今後の市場を独自に分析
今後、首都圏の新築マンション市場はどのように推移していくのでしょうか。ここからは、管理組合運営や既存マンションの価値判断に影響する観点で整理します。
価格高止まりと供給抑制は続くか
まず、建設費の高騰や用地取得難といった根本的な課題がすぐに解消されるとは考えにくく、新築マンションの価格は当面高止まりする可能性が高いと言えます。特に都心部においては、大手デベロッパーによる高額物件の供給が続くことで、平均価格を押し上げる力が働くと予想されます。
一方、供給戸数については、中小デベロッパーの慎重な用地取得姿勢や、大規模開発の難しさから、低い水準での推移が続く可能性があります。ただし、大手デベロッパーが都心部での供給を強化する動きや、再開発プロジェクトの進展によっては、局地的に供給が増加する可能性も考えられます。
【契約率低迷と在庫増加の行方】買い手市場への転換は限定的か
初月契約率の低迷と販売在庫数の増加は、一見すると買い手市場への転換を意味するようにも見えます。しかし、価格の高止まりという状況を考慮すると、買い手市場への本格的な転換は限定的であると考えられます。
消費者は価格に見合った価値をより慎重に見極めるようになり、立地や設備、ブランド力などを重視する傾向が強まるでしょう。そのため、魅力的な物件とそうでない物件の二極化がより鮮明になり、立地の悪い物件や割高な物件は、販売に苦戦する可能性が高まります。
【新たなニーズへの対応】コンパクトマンションや郊外物件の可能性
今後は、価格の高騰を踏まえ、消費者の新たなニーズに対応した物件供給が重要になると考えられます。例えば、都心部においては、単身者やDINKS層をターゲットとしたコンパクトマンションの需要が根強いと考えられます。また、郊外においては、テレワークの普及などを背景に、広めの住戸や自然豊かな住環境を求める層が増加する可能性があり、価格とのバランスが取れた物件であれば、一定の需要が見込めるでしょう。
※新築供給減少局面で注目される「コンパクト・ワンルーム系物件」の管理リスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。
【中古マンション】立地の良いマンションを中心に価格上昇
首都圏の新築マンション市場においては、供給戸数の過去最少記録、建設費や用地費の高騰による平均価格の上昇といった状況が見られています。このような背景から、中古マンション市場においても新たな動きが予測されます。
特に、立地の良い中古マンションを中心に、2025年度も引き続き価格は上昇傾向にあると考えられます。新築マンションの価格高騰により、これまで新築を検討していた層が、利便性の高いエリアの中古マンションに目を向ける可能性が高まります。都心部においては新築の大規模マンション開発が難しくなっているという分析もあり、既存の好立地マンションの希少価値が高まることも予想されます。
また、今後は管理面における既存マンションの選別もより一層進むと考えられます。新築マンションの供給が絞られる中で、既存の住宅ストックの価値が見直される傾向が強まるでしょう。適切な修繕計画や行き届いた管理体制が整っているマンションは、居住者にとって快適な住環境を提供するだけでなく、資産価値の維持・向上にもつながります。そのため、良い管理のマンションは、立地に加えてさらに価値が上昇する可能性を秘めていると言えるでしょう。
以上のことから、今後の首都圏の中古マンション市場においては、立地の良さはもちろんのこと、マンションの管理体制が購入を検討する上での重要なポイントとなると考えられます。これらの要素を兼ね備えたマンションは、競争が激化する不動産市場において、より高い評価を得るのではないでしょうか。
【政策や金融情勢の影響】今後の市場変動要因
今後の市場動向を左右する要因としては、政府の住宅政策や金融情勢も無視できません。住宅ローン金利の変動や、税制優遇措置の変更などは、消費者の購買意欲に直接的な影響を与える可能性があります。また、都市再開発やインフラ整備の動向も、特定のエリアの不動産価値を大きく左右する可能性があります。
【結論】供給絞り込みと価格高騰が続く首都圏マンション市場、賢い選択が求められる
2024年度の首都圏新築マンション市場は、供給戸数の大幅な減少と価格の高騰が際立つ結果となりました。背景には、建設コストの上昇や用地取得難といった構造的な問題があり、中小デベロッパーは苦境に立たされています。大手デベロッパーは都心部の高額物件に注力する一方で、消費者の間では戸建て住宅へのシフトや、よりコストパフォーマンスの高い物件を求める動きが見られます。
今後もこの傾向は続くと予想され、首都圏のマンション市場は二極化が進むと考えられます。このような状況下では、管理組合や既存マンションの居住者にとっても、管理状態や立地が将来価値を左右する重要な判断軸となります。自身のライフスタイルや経済状況を慎重に考慮し、将来的な価値も見据えた賢い選択が求められるでしょう。
デベロッパーにとっては、多様化する消費者ニーズを的確に捉え、魅力的な物件を適正な価格で供給していくことが、持続的な成長のカギとなると言えます。
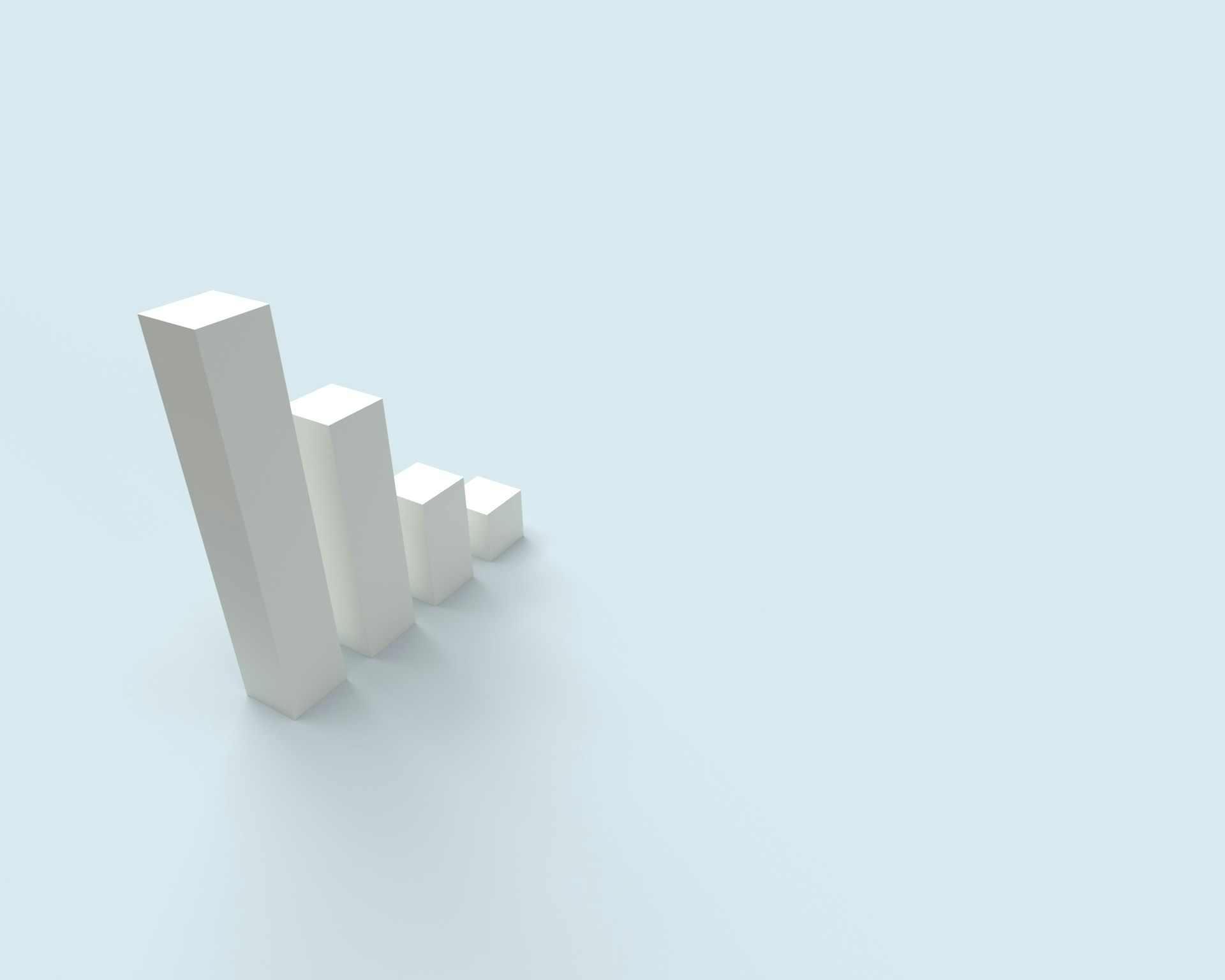





コメント